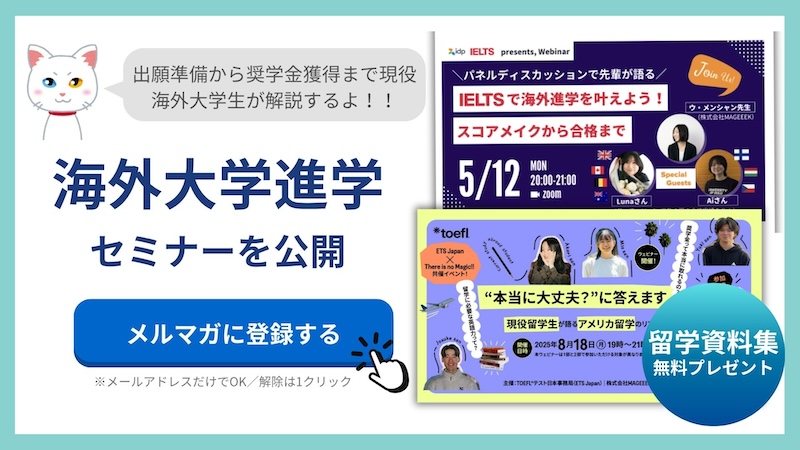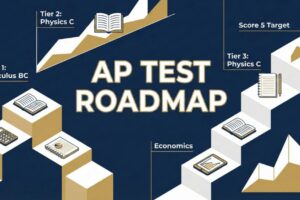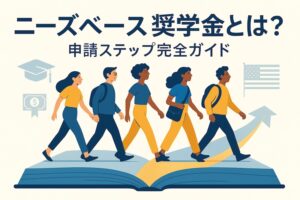アメリカの大学で「国際関係学」を学びたい——。
そう思っても、どんな大学があるのか、入学条件や費用はどのくらいなのか、具体的なイメージがつきにくいのではないでしょうか。
国際関係学は、政治・経済・歴史・地域研究など幅広い分野を横断し、国際社会で活躍する力を育む学問です。
アメリカには世界的に有名な大学から、日本人学生が多く学ぶ中堅大学まで、選択肢が数多くあります。
この記事では、アメリカで国際関係学を学ぶ魅力や学べる内容、おすすめ大学、費用や入学条件、卒業後のキャリアまでを整理しました。
まだ志望校が決まっていなくても大丈夫。
全体像を知ることで、自分やお子さんに合った大学選びの第一歩を踏み出すことができます。
目次
アメリカの大学で国際関係学を学ぶ魅力
国際政治の中心で学べる
アメリカ、とくにワシントンD.C.やニューヨークは、世界の国際政治の中心地です。
ホワイトハウスや国務省、国連本部、数多くのシンクタンクやNGOのオフィスが、大学キャンパスから地下鉄で数駅先にあるのが日常。
授業で取り上げた国際問題が、翌日の新聞の一面や街頭の抗議デモとして現実に目の前に広がることも珍しくありません。
たとえば、午前中に「中東和平交渉」について学んだ後、午後には国連本部の前で実際に市民団体の活動を目にする──そんな環境はアメリカだからこそ体験できるものです。
日本の高校生や保護者からすると遠い世界に感じる国際政治が、アメリカでは日常の延長線上にあります。
この「現実と学びの距離の近さ」が、国際関係学をアメリカで学ぶ最大の魅力のひとつです。
多国籍の学生と交流できる環境
国際関係学を学ぶ学生は、アメリカ人だけではありません。
アジア、アフリカ、中東、ヨーロッパ、中南米──世界中から「外交官になりたい」「NGOで働きたい」「国際ビジネスを動かしたい」と考える同世代が集まります。
授業のディスカッションで隣に座るのは、将来国を代表する外交官を目指す中東出身の学生かもしれません。
課題を一緒に進める相手は、国際協力に情熱を持つアフリカの学生かもしれません。
日本国内にいてはなかなか出会えない仲間と共に学ぶことで、自分の視野が自然に広がっていきます。
文化や価値観が異なる仲間と議論を重ねる経験は、「自分の意見を持ち、相手の考えを尊重する力」を育てます。
それは、将来どんなキャリアを選んでも必ず生きる力になります。
実習・インターンシップの豊富さ
アメリカの大学は「学んだことを実際に使う」機会が多いのも大きな特徴です。
特にワシントンD.C.では、国務省や世界銀行、国際NGOやシンクタンクでインターンをする学生が数多くいます。
授業が終わったら地下鉄に乗って国務省へ。金曜日は授業を午前で切り上げ、午後からは国際人権NGOのインターンへ
──そんな生活は、アメリカの大学生にとって決して特別なことではありません。
さらに、多くの大学ではインターンシップやフィールドワークが単位として認められており、卒業要件の一部にも組み込まれています。
つまり「実践経験を積むこと」が制度的に保証されているのです。
学んだ理論をすぐに現場で試し、卒業と同時に実務経験も持っている。これこそ、アメリカで国際関係学を学ぶ大きなアドバンテージです。


国際関係学とは?学べる分野とキャリアの広がり
国際関係学で扱う主な分野(政治学・経済・地域研究・歴史・国際法)
国際関係学は、国と国との関わりや世界の動きを理解するために、複数の学問を組み合わせて学ぶ分野です。
- 政治学: 外交政策や国際交渉の仕組みを理解する。
- 経済学: 貿易や開発援助、グローバル経済の動きを読み解く。
- 地域研究: アジア、中東、ヨーロッパなど特定の地域に焦点を当て、その社会・文化・政治を掘り下げる。
- 歴史: 現代の国際問題の背景を知るために、戦争や条約、冷戦などを研究する。
- 国際法: 国連憲章や国際条約、人権問題を法的にどう扱うかを学ぶ。
教科書的に知識を覚えるだけでなく、ディスカッションやケーススタディを通して「どうすれば平和的に解決できるか」「どの政策が現実的か」といった“答えのない問い”に挑むのが特徴です。
卒業後のキャリア例(国際機関・外交官・ジャーナリスト・外資系企業・研究職)
国際関係学を学んだ後の進路は、一つに限られません。むしろ学際的な学びだからこそ、多彩なキャリアに広がっていきます。
- 国際機関やNGO: 国連や世界銀行、国境なき医師団などで国際協力に携わる。
- 外交官・政府機関: 外務省や国際政策に関わる省庁で、日本や世界の政策を動かす役割を担う。
- ジャーナリスト・メディア関係: 国際ニュースを現地で取材し、世界の動きを伝える。
- 外資系・グローバル企業: 国際市場を相手に戦略を立てる、商社や多国籍企業でのキャリア。
- 研究職・教育者: 大学院でさらに専門を深め、大学やシンクタンクで研究を続ける。
「国際関係学=外交官養成」ではなく、学んだ分析力・語学力・多様な文化を理解する力をベースに、幅広い分野で生かせるのが大きな強みです。


国際関係学に強いアメリカの大学【おすすめ】
ジョージタウン大学:外交学部の名門
ワシントンD.C.にあるジョージタウン大学の外交学部(School of Foreign Service, SFS)は、世界でもっとも有名な国際関係学部のひとつです
キャンパスから数キロ先にはホワイトハウスや国務省があり、授業と現実の国際政治が直結しています。
学生は国際法や安全保障、開発経済などを専門的に学びつつ、国連やシンクタンクでのインターンを経験できるチャンスも豊富。
多くの卒業生が外交官や国際機関、外資系企業で活躍しています。
ハーバード大学:公共政策・国際研究に強み
世界トップの名門校として知られるハーバード大学は、国際関係学でも圧倒的な存在感を誇ります。
特にケネディ・スクールを中心に、公共政策や国際安全保障、グローバル経済政策などを学べる機会が整っています。
学部レベルでも政治学や国際関係を幅広く学べるため、将来的に大学院進学を視野に入れる学生にとって理想的な環境です。
学内外で開かれるシンポジウムや講演会には、世界のリーダーや実務家が集まり、刺激的な学びの場となっています。
スタンフォード大学:国際関係×テクノロジー
シリコンバレーの中心にあるスタンフォード大学は、国際関係学にテクノロジーやデータ分析を組み合わせた教育が特徴です。
専攻では政治・経済・歴史に加え、統計やデータサイエンスのスキルも重視され、現代の国際課題を多角的に理解できるように設計されています。
また、語学習得と留学が必須とされ、実際に海外で生活・学習する経験を通して国際感覚を磨ける点も魅力です。
国際問題を「現場」と「データ」の両面から捉える力を育てられるのがスタンフォードならではです。
コロンビア大学:ニューヨークの立地を活かした実践教育
ニューヨークに位置するコロンビア大学は、国連本部や国際NGO、メディア企業に近接しているため、実践的な国際関係学を学ぶのに理想的な環境です。
授業で学んだ理論を、そのまま現場でのインターンやリサーチに応用できる機会が豊富にあります。
ジャーナリズムや人権問題、国際経済など、多様なプログラムと都市のリソースを組み合わせた学びが可能です。
ニューヨークという国際都市で暮らしながら、国際関係を肌で感じられるのは大きな強みです。
その他の選択肢:中堅〜準上位大学の国際関係学
| 大学名 | 特徴・強み |
| American University(アメリカン大学) | ワシントンD.C.に位置。国際関係学部は米国内最大規模で、国務省や国際機関へのインターン参加率が高い。 |
| George Washington University(ジョージ・ワシントン大学) | 首都の立地を活かし、国務省やシンクタンクとのつながりが豊富。Elliott Schoolで国際関係×公共政策を学べる。 |
| University of California, Berkeley(カリフォルニア大学バークレー校) | 社会科学分野に強み。政治学・地域研究に評価が高く、多様な学生層と刺激的な学びが可能。 |
| University of California, San Diego(カリフォルニア大学サンディエゴ校) | 国際関係と経済学を組み合わせた実践的カリキュラム。アジア太平洋研究でも注目される。 |
| University of California, Los Angeles(カリフォルニア大学ロサンゼルス校) | 国際関係・政治学で高い研究水準を持つ。多文化都市ロサンゼルスで学べる環境。 |
| Florida International University(フロリダ国際大学) | マイアミという多文化都市に立地。ラテンアメリカ研究に強く、条件付き入学制度もある。 |
| Syracuse University(シラキュース大学) | 公共政策と国際関係の融合教育に定評。大学院進学と連携したカリキュラムが魅力。 |
| University of Denver(デンバー大学) | 国際安全保障や開発分野に特色。冷戦期から続く伝統的な国際関係学スクール。 |
| Tufts University(タフツ大学) | ボストン近郊のリベラルアーツ校。フレッチャー外交大学院を併設し、少人数教育で議論を深められる。 |
| Middlebury College(ミドルベリー大学) | 外国語教育と国際研究に強い小規模校。留学生比率も高く、国際的な学習環境。 |
| Macalester College(マカレスター大学) | リベラルアーツ校ながら外交・国際政治志向が強い。多文化都市セントポールで学べる環境。 |


アメリカ大学留学の費用と奨学金
学費と生活費の目安(州立大学 vs 私立大学)
アメリカの大学進学で最も大きな負担は学費と生活費です。
- 私立大学(ハーバード、ジョージタウンなど)では、授業料だけで年間7万ドル前後(約1,000万円)。寮費や食費、保険料を含めると年間900万〜1,100万円規模になることもあります。
- 州立大学(UC系など)でも、留学生は「州外授業料」がかかるため、授業料は年間4万〜5万ドル程度。生活費を含めると600万〜800万円ほどが目安です。
都市によって生活費も大きく異なり、ニューヨークやワシントンD.C.は特に高額。
一方、地方都市や中西部の大学は生活費が比較的抑えられます。
大学独自の奨学金制度
多くの私立大学は「返済不要の奨学金(Need-based Scholarship)」を設けています。
- プリンストン大学やハーバード大学などは、留学生も対象に家計状況に応じて学費を全額免除するケースがあります。
- 一方、ジョージタウンやGWUなどは、成績優秀者に授業料の一部を免除する「メリットベース奨学金」も提供しています。
ただし、申請の際には成績証明や家計書類(確定申告書、銀行残高証明など)を英語で提出する必要があるため、準備は早めが安心です。
日本から申請できる奨学金(JASSOや民間財団)
アメリカの大学独自の奨学金だけでなく、日本国内から申請できる制度も活用可能です。
- JASSO海外留学支援制度:返済不要。成績・計画書・進学先の条件を満たせば月額5〜10万円程度が支給されます。
- 民間財団(例:柳井正財団、伊藤国際教育交流財団など):授業料や生活費の一部を支援。対象者や条件は財団ごとに異なり、応募時期も早めに始まります。
大学の奨学金と併用できる場合もあるので、情報収集は欠かせません。
卒業後のキャリアと進路
国際機関やNGOでのキャリア
「世界を動かす場所で働きたい」——そんな想いから国際関係学を選ぶ学生は少なくありません。
実際、大学在学中に国連や世界銀行でインターンを経験し、その後フルタイム職員として採用されるケースもあります。
現場に出れば、机上の理論ではなく“人の命や生活”に直結する課題に向き合うことになります。
教育支援や人権保護、環境問題などに携わり、国境を越えて社会に貢献できるのは、国際関係学ならではの道です。
外資系・国際企業への就職
「国際関係=外交官や国連」と思われがちですが、それだけではありません。
国際関係学で培ったのは、異なる価値観を理解し、データや事例をもとに判断する力。これらはグローバル企業にとっても強く求められています。
実際に、商社や外資系コンサルティング会社に就職し、海外出張やプロジェクトで世界を相手に仕事をする卒業生も多いです。
学生のうちからニューヨークやワシントンD.C.の企業でインターンをして、卒業と同時に就職につなげる人も珍しくありません。
「国際関係学=就職が狭い」ではなく、「使える業界が幅広い」と考えるのが現実的です。
大学院進学で専門性をさらに深める
国際関係学を学んだ後、さらに一歩踏み込みたい学生は大学院に進学します。
たとえば「安全保障をもっと突き詰めたい」と思えば公共政策大学院へ、「アジアの歴史と政治を深めたい」と思えば地域研究の大学院へと進む道があります。
大学院ではリサーチ力や政策提言力を磨けるため、国際機関の専門職や政府の政策担当など、より高度なキャリアにつながりやすいのが特徴です。
「学んだことを武器に社会を動かしたい」という学生にとって、大学院進学は挑戦の次のステージになります。

アメリカ大学進学ならThere is no Magic!! の並走型出願サポート
アメリカ大学への出願準備は、学力や英語力だけでなく、エッセイ、課外活動、奨学金申請まで幅広い準備が必要です。
多くの学生や保護者が「どこから始めたらいいのか」「この方向性で正しいのか」と不安を抱えるのは当然のことです。
There is no Magic!! の「並走型出願サポート」では、そんな不安を抱えた段階から相談可能。
情報収集の初期段階でも、自己分析や大学選びの方向性を一緒に整理できます。
ディスカッションを重ねる中で、「やっぱりアメリカではなく他の国が自分に合っているかもしれない」という気づきが生まれることもあります。
それもまた、正しい方向に進むために大切なプロセスです。
実際のサポートでは、
- 最長3年間、複数メンターが伴走
- エッセイの作成・添削、課外活動の整理、奨学金申請の準備まで一貫支援
- 合格実:ジョンズ・ホプキンス大学、トロント大学、ジョージ・ワシントン大学、カーネギーメロン大学など多数(奨学金付き合格者も多数)
受講生の 88%が奨学金を獲得 し、難関大学への合格実績も豊富です。
悩み始めた段階から相談しながら、自己分析を通じて「本当にやりたいこと」を言語化し、進学に向けた最適なプランを描くことができます。
まずは無料カウンセリングで、自分に合った進学の形を一緒に考えてみませんか?

まとめ:アメリカで国際関係学を学ぶ第一歩
アメリカで国際関係学を学ぶことは、決して簡単な道ではありません。
学費や入試、英語力、そして生活のことまで考えると、不安や迷いが生まれるのは自然なことです。
でも同時に、この学びは「世界の課題を自分ごととして捉え、社会を動かす力」を育ててくれます。
ワシントンD.C.やニューヨークといった国際政治の中心で学ぶ経験、多様な学生と交わる日常、そして実習やインターンを通じて現場を知る機会。それらは、日本ではなかなか得られない学びです。
今すぐ進学先を決める必要はありません。
まずは「どんな大学があるのか」「自分はどんなテーマに関心があるのか」を知るところから始めてみましょう。
小さな一歩を積み重ねるうちに、進むべき道は自然と見えてきます。
今日の関心を、明日の行動につなげていきましょう。