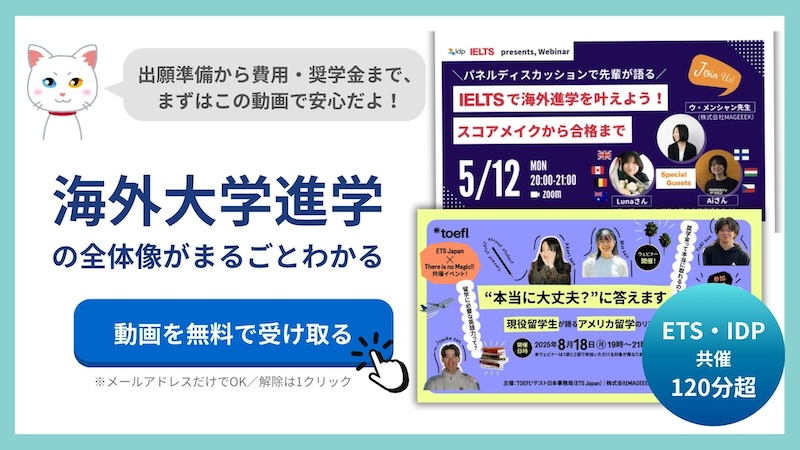「アメリカとイギリスの大学って、どんなふうに違うんだろう?」
海外進学を考え始めた高校生や保護者の方なら、一度は気になったことがあるのではないでしょうか。
アメリカはリベラルアーツ教育で幅広く学べる4年制、イギリスは専攻を決めて3年間で専門を深めるスタイルが基本。
出願準備やエッセイの書き方、学費や卒業後の進路まで、それぞれの国には大きな特徴と違いがあります。
例えば、日本の高校からアメリカには直接出願できる一方で、イギリスでは「ファウンデーションコース」を経て名門大を目指すルートが一般的。
エッセイもアメリカは「自分の価値観や経験」を自由に描くのに対し、イギリスは「なぜその学問を学びたいのか」を学術的に示す、と大きく異なります。
この記事では、アメリカとイギリスの大学の違いを 制度・学び方・費用・学生生活・キャリア の観点から整理し、実際の準備や進学後の生活をイメージできるように解説します。
読み終える頃には、「自分にはどちらが合っているか」のヒントが見えてくるはずです。
目次
学位制度・学び方の違い
アメリカの大学:4年制とリベラルアーツの柔軟さ
アメリカの大学は基本的に4年制です。
最初の2年間は「リベラルアーツ教育」と呼ばれる幅広い教養科目を学び、その後に専攻(メジャー)を選ぶ仕組みになっています。
入学時点で「まだやりたいことがはっきり決まっていない」という学生も、数学・心理学・ビジネス・コンピュータサイエンスなど多様な分野を体験しながら、自分の興味に合った専攻を見つけることができます。
専攻を途中で変更するのも珍しくなく、進路を柔軟に考えたい人にとって大きな魅力です。
イギリスの大学:3年制で早くから専門を深める
イギリスの大学は通常3年制(スコットランドは4年)で、入学時点で専攻を決める必要があります。
1年目からその分野の専門教育が始まるため、短期間で専門性を高められるのが特徴です。
たとえば「国際関係を学んで外交官を目指したい」「経済学を研究して将来はシンクタンクに進みたい」といったように、明確な目標を持つ学生には効率的で実践的な環境といえるでしょう。
- やりたいことがまだ探している段階 → アメリカの大学向き
- やりたいことが明確で、早くから専門を深めたい → イギリスの大学向き
自分やお子さんが「どちらのタイプに近いのか」を考えることが、留学先を選ぶ上で大切な第一歩です。


入試制度と出願準備の違い
アメリカの大学:総合評価と多面的な準備
アメリカの大学入試は、いわゆる「総合評価型」です。必要な要素が多く、準備には時間がかかります。
- 学力テスト:SATまたはACT
- 英語力試験:TOEFLまたはIELTS
- エッセイ:共通エッセイに加え、各大学のサプリメンタルエッセイがあり、10本以上書くことも珍しくありません
- 推薦状・課外活動:学外活動やリーダーシップ経験も重視されます
特にエッセイは「あなたはどんな人か」を伝える重要なパート。
たとえば「なぜ映画が好きか」というテーマなら、幼少期の体験や自分を形づくった出来事を交え、人柄や価値観を描き出すことが求められます。
イギリスの大学:UCASと学問適性重視
イギリスの大学出願は、UCAS(ユーカス)という共通システムを通じて行います。
最大5校まで同時に出願可能で、評価の中心は高校の成績です。
日本の一般的な高校課程から直接入学するのは難しく、ファウンデーションコース(1年間の準備課程)を経て進学するのが一般的です。
UCL(ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン)などは自校のファウンデーションを運営しており、好成績を収めればそのまま学部進学が可能です。
ただし、オックスフォードやケンブリッジは基本的にファウンデーションを認めず、AレベルやIBといった国際資格が必要です。
エッセイにあたるPersonal Statementは全大学共通で1本だけ提出します。
内容は学術的で、「なぜこの専攻を学びたいのか」「どんな準備をしてきたのか」を論じることが求められます。
- アメリカ → 「映画が人生に与えた影響や、自分の物語」を自由に語る
- イギリス → 「どんな映画理論や作品を学んできて、それを大学でどう深めたいか」を論じる
- アメリカ → 「高校時代に参加したエコ活動やボランティア」を強調
- イギリス → 「科学的な研究経験や専門的知識への興味」を示す
このように、アメリカは人物像全体を、イギリスは学問への適性を重視する、という違いがはっきりと表れます。

授業スタイルと評価方法の違い
アメリカの大学:ディスカッションと平常点を重視
アメリカの大学は、少人数制の授業が多く、教授や学生同士のディスカッションが日常的に行われます。
授業では「あなたはどう思う?」と意見を求められることが多く、積極的に発言する姿勢が評価につながります。
成績は課題・小テスト・プレゼン・出席など平常点が大きな割合を占め、毎週の積み重ねが重要です。
つまり、入試でエッセイや課外活動を通じて「自分を表現できるか」が問われるのは、大学に入ってからも同じ。
日常的に発言し、考えを形にする力が求められる環境です。
イギリスの大学:講義と自主学習、試験での一発勝負
イギリスの大学は講義中心で、授業時間よりも自主学習に重きが置かれます。
教授は大枠の知識を示し、細かい理解や応用は学生が自分で読み込み、論文やリサーチを通じて深めていきます。
成績は期末試験や長文のエッセイ、研究論文などに大きく依存し、授業中の発言や出席はほとんど評価に含まれません。
この仕組みも、出願準備とつながっています。
Personal Statementで「学びたい分野への適性」を論じるように、大学に入ってからも専門分野を自ら深める姿勢が強く求められるのです。
- アメリカ:「自分を表現できる人材」を求め、大学でも表現力と継続的な努力を重視。
- イギリス:「学問への適性」を問われ、大学でも主体的に学びを深める力が評価。
受験で問われること=大学生活でも求められること。
これを理解すると、自分に合った進学先をより具体的にイメージできるでしょう。


費用・奨学金・留学期間の違い
アメリカの大学:高額だが奨学金の選択肢が豊富
アメリカの大学の学費は世界的にも高いことで知られています。
州立大学であっても、留学生は「州外扱い」となるため、年間の学費は私立と大きく変わらないこともあります。
授業料だけで年間2〜5万ドル(約300万〜750万円)、生活費を含めると年間500万〜800万円程度かかるケースも珍しくありません。
一方で、奨学金の種類は豊富です。成績優秀者向けのメリットベース奨学金や、家計状況に応じたニーズベースの奨学金を提供する大学もあります。
準備が大変な反面、条件を満たせば学費の一部免除や生活費補助を得られるチャンスが多いのも特徴です。
さらに、アメリカは学部4年に加えて大学院進学も一般的で、修士課程を含めると学習期間は5〜6年に及ぶこともあります。
その分、教育投資としては大きな金額になります。
イギリスの大学:短期間集中で総額を抑えやすい
イギリスの学部課程は通常3年制(スコットランドは4年)で、修士も1年で修了できるのが一般的です。
そのため、同じ学位を得る場合でも、アメリカより短期間で終えられる分、イギリス大学の学費は総額では抑えやすい傾向があります。
ただし、日本の一般的な高校課程からは直接出願が難しいため、多くの学生はファウンデーションコース(1年間)を経由します。
ファウンデーションは学費と生活費で年間300万〜400万円程度が必要になるため、実際には「3年+1年=4年間」と考えるとアメリカと大きく差がないこともあります。
とはいえ、修士課程が1年で済む点は大きなメリットで、将来大学院進学を考える人にとってはトータルでアメリカよりコストを抑えやすい選択肢といえるでしょう。
- アメリカ:年間500万〜800万円 × 4年(+修士2年)
- イギリス:学部3年(+ファウンデーション1年)で総額はアメリカよりやや抑えやすい/修士は1年で短期集中
つまり「学費が高くても奨学金のチャンスが多いアメリカ」か、「期間が短く総額を抑えやすいイギリス」か。
家庭の負担や進学後のキャリアプランに合わせて検討することが大切です
学生生活とキャンパス文化の違い
アメリカの大学:広大なキャンパスと活発なコミュニティ
アメリカの大学生といえば、映画やドラマに出てくるような広大なキャンパスと寮生活が特徴です。
多くの大学では1年目は寮に入るのが一般的で、ルームメイトやフロアの仲間と共同生活を送りながら、人間関係を築いていきます。
また、スポーツやクラブ活動の盛んさも魅力の一つ。フットボールやバスケットボールの試合は大学全体のイベントになり、地域住民も巻き込んだ一大行事です。
勉強だけでなく、課外活動やイベントも学生生活の大切な要素として組み込まれています。
「学問も大事だけれど、仲間と一緒に熱いキャンパスライフを送りたい」という人には、アメリカの大学生活はぴったりです。
イギリスの大学:都市に溶け込む落ち着いた学生生活+旅のしやすさ
イギリスの大学は、アメリカほどキャンパスが独立していないことが多く、都市や町に溶け込んだ環境にあります。通学スタイルの学生も少なくありません。
スポーツやクラブ活動もありますが、アメリカのように派手で全員参加型というよりは、自主的に取り組む課外活動という雰囲気です。
大学によってはカレッジ制を導入しており(例:オックスフォード、ケンブリッジ)、学生はカレッジという小さなコミュニティに所属し、学習・生活・交流を支え合います。
伝統的な式典やフォーマルディナーなど、イギリスならではの文化を体験できるのも特徴です。
さらに、旅好きな人にとってイギリスは魅力的です。
格安航空(LCC)を使えば週末にパリやローマなどヨーロッパ各国へ気軽に旅行でき、学問と並行して世界を体験するチャンスが広がります。
「落ち着いた環境で学びたい」「ついでにヨーロッパを旅してみたい」という人には、イギリスの学生生活は非常に相性が良いといえるでしょう。
- 賑やかなキャンパスでイベントや活動を楽しみたい → アメリカ向き
- 歴史や伝統に触れつつ、勉強を中心に落ち着いた生活を送りたい/旅行も楽しみたい → イギリス向き
学費や制度だけでなく、「毎日の生活がどんな雰囲気か」を想像すると、より自分に合った留学先を選びやすくなります。


卒業後の進路とキャリアの違い
アメリカ・イギリスどちらの大学を卒業しても、修士進学や現地での就労制度を活用してキャリアにつなげることができます。
大きな違いは制度と期間です。
- アメリカ:OPT制度を利用すれば、専攻によっては最長3年間の現地就労が可能。修士課程は2年が主流。
- イギリス:Graduate Routeで学士・修士は一律2年、博士は3年間の就労が可能。修士は1年で修了できるため、社会に出るまでの年数を短縮しやすい。
つまり、どちらも進学後のキャリアパスは広く開かれていますが、「現地就労の期間」や「修士の年限」に違いがあるのがポイントです。
実際に進学した学生の声
アメリカの大学で学ぶ先輩たち
Claireさん(リベラルアーツ大・社会学専攻)
「アメリカのリベラルアーツ大学では、社会学と映画を組み合わせて学ぶことができました。自分の興味を自由に設計できる環境のおかげで、視野が広がったと思います。挑戦するハードルが下がり、新しいことに積極的に取り組めるようになりました。」
Hinataさん(North Central College・美術&音楽専攻)
「アメリカでは美術とジャズを同時に学ぶことができ、専攻を1つに絞る必要がありませんでした。最初は英語での発言に躊躇しましたが、周囲の雰囲気に後押しされて間違いを恐れず挑戦できるようになりました。幅広い学びと挑戦を通じて、自分の『好き』を自信に変えられたのはアメリカならではの経験です。」
池田隼さん(カリフォルニア工科大学・数学&CS専攻)
「カリフォルニア工科大学では数学とCSをダブルメジャーにしました。課題はとてもハードですが、その分、世界最先端の研究に触れる機会が豊富です。教授や仲間と協力して難問に挑む日々を通して、『基礎を学びつつ常に新しい知に触れる』という姿勢が身につきました。」

イギリスの大学で学ぶ先輩たち
Lunaさん(UCL・政治学専攻)
「UCLではArts and Sciences専攻で幅広い分野を学んでいます。ロンドンは文化資本が豊かで、大英博物館に気軽に通えるのも魅力。多国籍な仲間と過ごす中で“自分の意見を言うこと”の大切さを学び、自分から動けば動くほど世界が広がると実感しました。」
さな子さん(ヨーク大学・美術史専攻)
「ヨーク大学では中世美術を専攻しています。入学当初はIELTS 5.5からのスタートでしたが、ディスカッションやエッセイ課題を通じて力がつきました。ヨークは自然と歴史ある街並みに恵まれ、安心して勉強に集中できる環境です。『自分で解決する力』や『多様な人とのコミュニケーション力』が鍛えられたのは、イギリスで学んだからこそだと思います」
Rionさん(マンチェスター大学・理系専攻)
「マンチェスター大学では心理学を専門的に学びました。課題やテストは大変でしたが、批判的に物事を考える力が鍛えられました。最初は海外で学ぶことに不安もありましたが、“挑戦してみればなんとかなる”という自信を得られたのは大きな収穫です。」

どちらが向いている?タイプ別の選び方
大学選びは「どちらが良いか」ではなく、「自分に合っているのはどちらか」を考えることが大切です。
アメリカの大学が向いている人
「まだ専攻を決めきれていない」
「いろんな授業を受けながら自分の興味を見つけたい」
「課外活動やクラブにも全力で取り組みたい」
――そんな人にとって、アメリカのリベラルアーツ教育や活発なキャンパス文化は大きな魅力です。
イギリスの大学が向いている人
「学びたい分野が明確にある」
「短期間で専門性を磨きたい」
「効率よく学位を取ってキャリアに進みたい」
――こうしたタイプには、イギリスの3年制学部や1年制修士がぴったりです。
では、あなたやお子さんはどちらでしょうか。
「まずは幅広く学びたい?」それとも「早くから専門を極めたい?」
この問いを自分に投げかけてみると、進むべき方向が少し見えてくるはずです。


海外大学進学ならThere is no Magic!! の並走型出願サポート
アメリカとイギリス、それぞれの大学には大きな違いがあり、どちらが自分に合うのか判断するのは簡単ではありません。
必要な英語試験やエッセイの書き方、奨学金制度も異なり、「この方向で正しいのかな?」と不安を感じるのは自然なことです。
There is no Magic!! の「並走型出願サポート」では、そんな段階から相談可能です。
- 最長3年間、複数メンターが伴走し、アメリカ・イギリス両方の出願に対応
- 自己分析や大学選びの整理を通じて、「本当に自分に合った進路」を一緒に見つける
- エッセイ添削、課外活動の整理、奨学金申請の準備まで一貫サポート
ディスカッションを重ねる中で、「やっぱりアメリカよりイギリスが合っているかもしれない」「大学院進学を視野に入れたい」など、新しい気づきが生まれることもあります。
それもまた、正しい方向に進むための大切なプロセスです。
豊富な合格実績
これまでに、
- アメリカ:ジョンズ・ホプキンス大学、ジョージ・ワシントン大学、カーネギーメロン大学など
- イギリス:エディンバラ大学、エセックス大学、マンチェスター大学など
- カナダやオーストラリア:トロント大学、ブリティッシュコロンビア大学、メルボルン大学など
世界中の難関大学への合格をサポートしてきました。さらに、受講生の88%が奨学金を獲得しています。
「アメリカかイギリスか迷っている」「何から始めたらいいのかわからない」という段階でも大丈夫。
まずは無料カウンセリングで、自分に合った進学の形を一緒に考えてみませんか?

まとめ:違いを知り、自分に合った進学先を選ぼう
アメリカとイギリスの大学は、学び方も生活も大きく異なります。
だからこそ大切なのは、どちらが良い・悪いではなく、自分に合う環境を知り、選んでいくことです。
「専攻を探しながら幅広く学びたい」「仲間と活発なキャンパスライフを送りたい」ならアメリカ。
「学びたい分野がはっきりしていて、効率よく専門を深めたい」ならイギリス。
もちろん、今の段階で「ここに絶対行きたい!」という大学が決まっていなくても大丈夫です。
むしろ、多くの人は「気になる国や大学を比較してみる」ところから準備を始めています。
情報を集め、準備を進める過程そのものが、留学への第一歩。
その積み重ねがやがて「ここで学びたい」と心から思える選択へとつながり、未来のキャリアや人生を大きく広げてくれるのです。