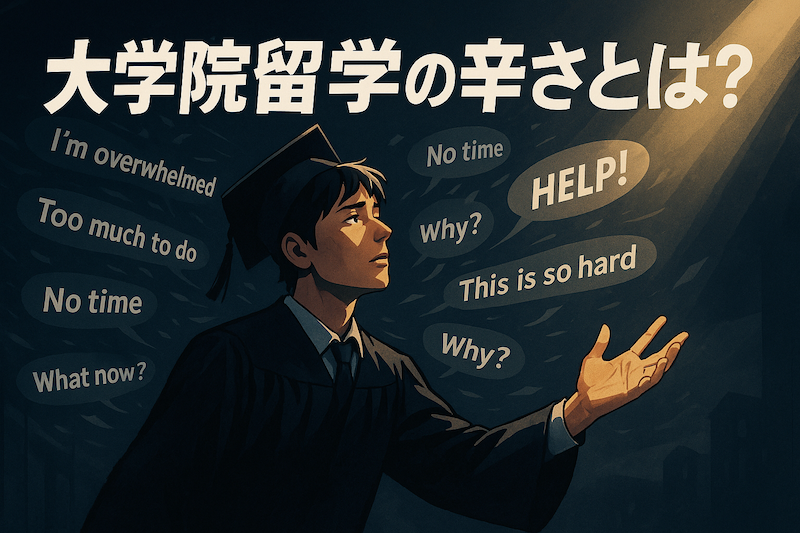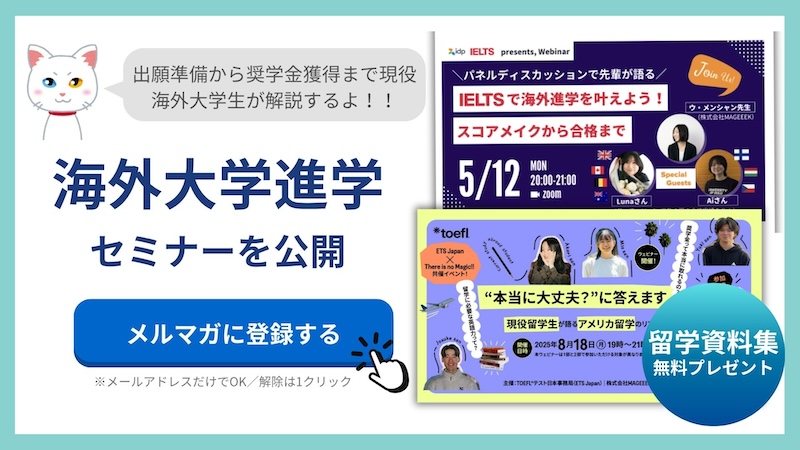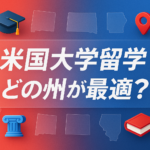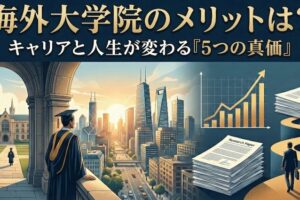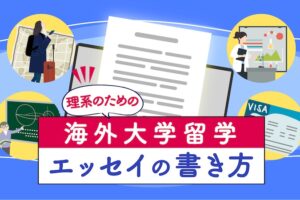大学院留学留学に興味はあるけれど、実際どれくらい大変なのか、英語についていけるのか、辛かったらどうしよう…と不安を抱える人はとても多いと思います。
ネットではキラキラした成功体験やメリットばかりが目につきますが、本当に知りたいのはそこではありませんよね。
最初の半年がどれだけ苦しいのか。何が一番辛いのか。自分は本当に耐えられるのか。
この“リアルな部分”が語られないからこそ、不安は膨らみ続けます。
だからこそ、この記事ではきれいごとは書きません。
多くの留学生が実際に直面する壁や、心が折れそうになる瞬間、そしてそれをどう乗り越えていくのかを率直に伝えます。
そのうえで、最初にひとつだけ伝えたいことがあります。「つらい」と感じるのは能力不足ではなく、大学院留学ではむしろ“当たり前”だということ。
この前提を知っているだけで、留学への向き合い方は大きく変わります。
ではまず、「大学院留学はつらい」という現実の正体から一緒に見ていきましょう。
- 最大の壁:授業より「雑談に入れない孤独感」や「資金不足で遊びを断る惨めさ」がメンタルを削る。最初の半年が正念場。
- 突破口:しかし、日本人の「真面目さと粘り」は海外で最強の武器になる。半年耐えれば必ず「適応」のスイッチが入る。
- リターン:英語力以上に、理不尽な環境を自力で生き抜く「サバイバル能力」と「自信」が一生の資産になる。
- 結論:辛いのは「成長している証拠」。挑戦しなかった後悔の方が、人生においては遥かに重い。
詳しくは記事本編で徹底解説!👇
目次
大学院留学で最初に襲ってくる“本当の辛さ”
大学院留学で最初にぶつかるのは、課題でも研究でもありません。「英語がわからない」という、どうしても逃げられない現実です。
授業の内容が難しいというより、まず“音”として聞き取れない。
ネイティブが普通のスピードで話すだけで、頭の中で処理が追いつかず、気がつけば会話はもう次の話題へ進んでいる。
その繰り返しが、毎日、何度も続きます。
英語が聞き取れない。会話に入れない。笑えない。
留学初期に最もつらいのは、授業よりも日常会話です。
ネイティブ同士の会話は、速度も話題の幅も広く、しかもジョークや皮肉が当たり前のように飛び交います。
周りが笑っているのに、自分だけ意味がわからない。
何か言いたくても、話題の流れに追いつけず、口を開くタイミングすらわからない。
その場に居るのに、そこに“いない”ように感じる瞬間が増えていきます。
「なんで自分だけ理解できないんだろう」
「こんなに英語を勉強したはずなのに…」
そんなふうに、自分が人より「遅れている」ことを突きつけられる日々。
日本での英語学習では決して味わわない、じわっと胸が痛むタイプの疎外感が積み重なります。
誰も責めていないのに、自分だけが置いて行かれるような感覚。これが多くの人にとって、最初の“本当の辛さ”です。
発言しないと成績が取れない大学院スタイル
そして追い打ちをかけるのが、大学院特有の“参加型スタイル”です。
授業に参加すること、議論に入ること、質問すること――これらがすべて成績に直結します。
理解できていなくても、英語に自信がなくても、発言しない=評価がつかない。
頭ではわかっているのに、口が開かない。言いたいことはあるのに、英語に変換する過程で自信がなくなる。
そんなことが毎日のように起きます。
「言いたいことはあるのに言えない」
「分かっているのに参加できない」
この矛盾こそが、留学初期の最大のストレスです。
そしてほとんどの人が気づきます。大学院留学の最大の壁は、学力ではなく“英語を使って戦うメンタル”だということ。
完璧に理解してから話すのではなく、「わからないなりに発言する勇気」が求められる。
これが、多くの人にとって予想以上にハードです。



意外と見落とされる「お金」の辛さ
留学前は「授業が大変そう」「英語についていけるかな」という不安の方が強いけれど、いざ生活が始まると、じわじわ効いてくるのが“お金”の問題です。
これは多くの人が事前に想像している以上に、メンタルに影響します。
授業の難しさや英語の壁は努力で何とかできるけれど、生活費は節約しても限界がある。
そしてこの「限界」が、日常のあらゆる場面で自分を追い詰めます。
パーティ・旅行・外食…みんなが楽しんでいる時ほど苦しい
留学生活では、クラスメイトからの誘いが頻繁にあります。
週末のパーティ、誕生日ディナー、学期休みの旅行。友達を作るチャンスでもあるし、本当は行きたい。
でも、自費で留学している人にとっては、こういう誘いほど胸が痛む瞬間はありません。
「ごめん、ちょっと今日は無理」
そう言いながら、本当は行けるお金がないだけ。
何度か断っていると、相手との距離が少しずつ開いていくのを感じる。
友達グループの写真をSNSで見て、「あの時、行けていたら今もっと仲良くなれていたんだろうな」と胸がぎゅっと締め付けられる。
いわゆるFOMO(取り残される不安)は、英語の壁より深く突き刺さることがあります。
孤独感は“イベントに行けない”という事実よりも、“経済的に選べない”という無力感から来るもの。
これは留学経験者しかわからない、独特の痛みです。
日本の感覚とは違う生活費の高さに心が削られる
さらに辛いのは、日常生活そのものが高額なこと。
家賃、光熱費、保険、交通費、食費…ほぼすべてが日本の倍近い。毎月の支払いを見るたび、ため息が出ます。
節約しようと思えば、
- 自炊ばかりで外食はほとんどできない
- 冬でも暖房を控える
- 教材は中古にする
- スタバで勉強できない(高いから)
そんな生活になっていきます。
そして結果的に、“節約しながら孤独に勉強する”という状況に追い込まれます。
もちろん、これは悪いことではない。むしろ多くの日本人留学生がこうやって乗り越えている。
でも、実際に続けてみるとわかります。お金のストレスは、予想よりずっとメンタルにくる。
英語ができなくても頑張れるけれど、お金に余裕がないと「選べない」「参加できない」瞬間が積み重なり、心が疲れていきます。


それでも日本人は“真面目さ×粘り”で必ず適応していく
英語がわからない、会話に入れない、イベントに行けない…。
最初の半年は本当に苦しい。
でも多くの日本人留学生を見ていて気づくのは、この時期を越えると、必ず“適応”のスイッチが入る瞬間が来るということです。
その鍵になっているのが、日本人の持つ「真面目さ」と「粘り強さ」。
これは留学環境で思っている以上に大きなアドバンテージになります。
課題は真面目にやれば何とかなる
まず、日本人の強さが一番発揮されるのが“課題”です。
海外大学院は課題の量こそ多いものの、一つひとつの難易度は「丁寧に調べて、時間をかけて取り組めば確実に仕上がるもの」が中心です。
- 読む量は爆増する
- リサーチは細かい
- エッセイも大量に書かされる
……それでも日本人の多くはこつこつ積み上げる作業が驚くほど得意です。
実際、こんな声をよく聞きます。
「英語はきついけど、課題はやれば終わるから安心できた」
「周りのネイティブが締切ギリギリでも、日本人は計画的に進めてた」
丁寧に作業する、日本語でも英語でもきちんと締切を守る、必要なところを細かく調べる——
こうした日本人の標準的な“勤勉さ”は、大学院では圧倒的な強みになります。
英語で苦戦しても、課題でしっかり点数を取れる。これが自己肯定感を支えてくれます。
英語は“半年間のもがき”で耐性がつく
英語に関しては、残念ながら“全部わかる日”は来ません。
ただ、多くの留学生は約3〜6ヶ月の“もがき期間”を越えたあたりで、英語に対する耐性が急に強くなっていきます。
その変化は派手ではないけれど、確実に起こります。
「わからない状態に慣れる」
最初の頃は、聞き取れないたびに落ち込み、理解できないたびに焦りが生まれます。
でも半年ほど経つと、
- 全部理解できなくても慌てない
- 部分的に拾って会話を成立させられる
- 自分の英語の“型”ができる
という“慣れ”が芽生えていきます。
「わからなくても動ける力」がつく
これは留学経験者が口を揃えて言う、大きな成長ポイントです。
わからないままでも授業に残る、質問する、議論に入る。要するに、不完全さのまま一歩踏み出せる力がつくんです。
「100%理解してから発言したい」——日本にいるときはこれが当たり前。
でも海外ではそれをしていたら一言も話せません。
だからこそ、“不完全でも進む”という新しい筋力が育つ。
これは英語力とは別物で、むしろ留学が人を成長させる最大のトレーニングです。
日本人は、真面目さと粘りの力で、最初の半年の苦しみを確実に越えていきます。
完全に理解しなくても動ける勇気、丁寧に積み上げる力。
この2つがそろったとき、留学生活は一気に“自分のもの”になっていきます。


大学院留学は辛さより“得られるもの”の方が圧倒的に大きい
ここまで読んで「留学って大変そうだな…」と感じたかもしれません。
実際、最初の半年は本当に苦しくて、自分の弱さと向き合う場面も多いです。
でも不思議なことに、大学院留学を経験した人で“行ったことを後悔している”という声はほとんど聞きません。
むしろ、後からじわじわと「あのとき行ってよかった」という確信が強まっていきます。
なぜかというと、留学の本当の価値は“英語”や“キャリア”だけではなく、人生そのものの軌道が変わるような経験にあるからです。
留学して後悔している人はいない。後悔するのは、行かなかった人。
まず現実として、1〜2年の海外生活で英語が完璧になる人はほとんどいません。
卒業後、日本で働いた方が年収が高いケースだって全然あります。
でも、それでも多くの人が言います。「行かなかった後悔の方がずっと苦しい」と。
留学は、行った瞬間からすべてが思い通りになるわけではありません。
むしろ失敗したり、言葉に詰まったり、孤独に耐えたりする日々が続きます。
それでも、「あの時、一歩踏み出した自分を誇りに思える」という感覚が、何年も経ってからじわじわと効いてくる。
行かない選択をした人の多くが、後になってこう言います。
「挑戦していたら、どんな人生があったんだろう」「一度くらい海外で暮らせばよかった」
この“もしも”は、時間が経つほど重くなる。
だからこそ、留学に挑戦した人は、その後の人生で振り返って後悔することがないのです。
自分の意見を持つ・言う自由が当たり前になる
海外では、授業でも日常でも“あなたはどう思う?”と必ず問われます。
意見を持つこと、率直に話すことが当たり前の文化。
最初は怖くても、続けるうちに「自分の考えを言ってもいいんだ」という意識が根づいていきます。
多様な価値観に触れ、世界の広さを肌で知る
国籍、宗教、バックグラウンド、人生の目的。
まったく違う人たちと関わることで、自分の“当たり前”が一度リセットされる。
そのリセットが、考え方の幅を一気に広げてくれます。
自分の人生を“自分で選ぶ”感覚が生まれる
海外生活では、毎日が選択の連続です。
どこに住むか、どんな友達を作るか、どの授業を取るか、どこに旅行するか。全部、自分で決める。
この「自力で人生を選ぶ感覚」が身についた瞬間、生き方そのものが変わります。
小さな成功体験が積み重なり、自己効力感が爆増する
- 英語で買い物ができた
- 現地の友達ができた
- プレゼンがうまくいった
- 論文をやりきった
こうした“小さな勝ち”が積み重なると、「自分はやればできる」という感覚が骨の芯まで染み込む。
これが留学後、仕事でも人生でも効いてくる。環境が変わっても、挑戦することが怖くなくなるからです。
留学は、楽しいことより苦しいことの方が多いかもしれません。でも、そこで得られる“経験”は、未来の自分を支え続ける土台になります。
辛さを乗り越えたあとに見える景色は、確実に行く前とは違う。
その景色を見た人が口を揃えて言うのが、「行ってよかった」というシンプルな一言です。


“経験から生まれる学び”は海外にしかない
正直な話、知識だけなら今の時代、どこでも学べます。
ビジネス理論もプログラミングも心理学も、YouTubeに無料で溢れているし、オンライン講座も本も山ほどある。
「学びたいだけなら、日本にいてもできるじゃん」これは事実です。
だからこそ、留学の価値は“知識”ではありません。
価値があるのは、自分の足で異国に立ち、言葉も文化も違う環境でもがきながら進む経験そのものです。
価値があるのは、「苦しむ・もがく・乗り越える」という“プロセス”
海外で生きるということは、毎日がちょっとした挑戦の連続です。
- スーパーで話しかけられて聞き取れない
- バスの乗り方がわからない
- 大学で急に発言を求められる
- 契約書を理解するのに1時間かかる
- グループワークで意見が通らない
こういう“生活の細部”の積み重ねが、自分の限界を広げ、メンタルの耐性を育てるトレーニングになる。
YouTubeや本で知識を得ても、このプロセスはどこにも載っていません。
“経験そのもの”が学びになるのは、海外に身を置いた人だけが味わえることです。
留学は“自己変革の装置”であり、学歴のためではない
多くの人が誤解しがちですが、留学の本質は学歴強化でも英語習得でもありません。
もちろんそれらも成果として手に入るけれど、もっと深い価値があります。
海外で生活すると、日常的に「あなたはどう思う?」と問われ続けます。
すると自然と、
- 自分の意見を持つ
- 相手と違う価値観を認める
- 自分の人生の舵を自分で切る
という“主体性の筋力”が育っていく。
留学が終わる頃には、「自分で決めていいんだ」という感覚がしっかり根を張っています。
これこそが自己変革。他の誰かがくれる学歴より、はるかに価値がある“内側の成長”です。
1〜2年の留学は、人生全体で見れば“投資として安すぎる”
留学は確かにお金がかかる。生活も大変だし、英語もすぐに上達しない。
キャリア面で短期的に見ると、日本に残った方が収入が高い場合だってあります。
それでも、人生全体で見れば1〜2年の留学は、驚くほどコスパの良い投資です。
なぜか?
- 自分の世界観が根本から広がる
- 多様な人とつながる人間性が身につく
- どんな環境でも生きていける自信が生まれる
- その後の人生に“挑戦する力”が残り続ける
これらは、一度身につくと一生失われない“資産”です。
留学は“英語を学ぶためのプロジェクト”ではありません。
一生ものの自分をつくるための、人生最大のブースト装置なんです。

海外大学院への挑戦を“ひとりで抱えない”という選択肢
大学院出願は、英語・書類・研究テーマ・出願戦略がすべて複雑につながっています。
それなのに多くの人が、「何から手をつければいいか分からない」「独学だと判断ができない」と立ち止まってしまいます。
There is no Magic!! 並走型出願サポートは、そんな“詰まる瞬間”を一緒に越えていく仕組みです。
出願の「優先順位」が一気にクリアになる
大学院は、SOP / PHS / Writing Sample など必要書類が多く、しかも学校ごとに求める内容が違います。
並走型では、あなたのバックグラウンドと志望校を整理し、「今はこれをやる」「これは後回しでいい」 と優先順位を明確化。
迷いが消えることで、着実に前へ進めるようになります。
自己分析と書類作成を、専門家が“横で伴走”
大学院のSOPは、学部よりも深い論理性とキャリア軸が必要。
独学だと方向性がブレやすく、何度書いても形にならないことが多いです。
並走型はメンターが質問を投げかけながら内容を言語化し、文章構成まで導きます。
実際に受講して合格をつかんだ社会人の方も、 「自分では気づけない強みや軸を引き出してもらえた」 と話しています
気軽に相談できる“ひとりじゃない環境”
出願準備は、孤独がいちばんの敵です。
並走型ではZoomやSlackでいつでも相談できる環境が整っており、悩みや書類の方向性をすぐに確認できます。
忙しい社会人でも、走り続けられる仕組みをつくっています。
- 社会人で、仕事と両立しながら出願をしたい
- SOPを何度書いても“しっくりこない”
- 専門分野の深堀りと文章化を一緒に進めたい
- TOEFL/IELTSの進め方や切り替え判断が難しい
- ひとりで抱えると不安が大きくなるタイプ
もし今「どこから手をつければいいか分からない」「この方向で合っているのか不安」と感じているなら、一度、無料相談で状況を聞かせてください。
必要なステップも、あなたに合う戦略も、一緒に整理できます。

大学院留学はつらい。でも、それ以上に“自分の人生を取り戻すチャンス”
大学院留学は、確かに簡単ではありません。
英語はわからないし、お金の不安もあるし、孤独な時間も少なくない。
ここまで読んで「やっぱり大変そうだな」と思った人もいるかもしれません。
でも、「辛いから行くべきではない」わけではありません。
むしろ、多くの人にとっては“辛いからこそ、自分が変わる時間になる”という面が大きいんです。
海外で暮らすと、これまで当たり前だった価値観がひっくり返り、自分の意見を持つ勇気や、自分で人生を選ぶ感覚が少しずつ育っていきます。
毎日の小さな挑戦が積み重なるうちに、「あれ、思っていたより自分は強いかもしれない」という感覚が芽生えてくる。
その上で、留学がくれるのは“環境の変化”だけではありません。
- 自分を支えてくれる友達との出会い
- 視野を一気に広げてくれる価値観
- 新しい挑戦に踏み出す勇気
- 不完全なままでも前に進める力
こうした変化は、机の上の学びでは絶対に手に入らないものです。
そして多くの留学生が振り返って言います。
「あの1〜2年が、人生の分岐点だった。」
辛い瞬間の方が多いかもしれないけれど、その先で出会う景色や成長は、人生を長い目で見たときに、必ずあなたを支えてくれます。
もし今、迷っているなら、その迷い自体が“踏み出したい気持ちがある”というサインなのかもしれません。
大学院留学は、あなたの人生を大きく動かすチャンスです。その一歩が、未来のあなたにとっての誇れる決断になりますように。
海外大学院留学 攻略記事一覧