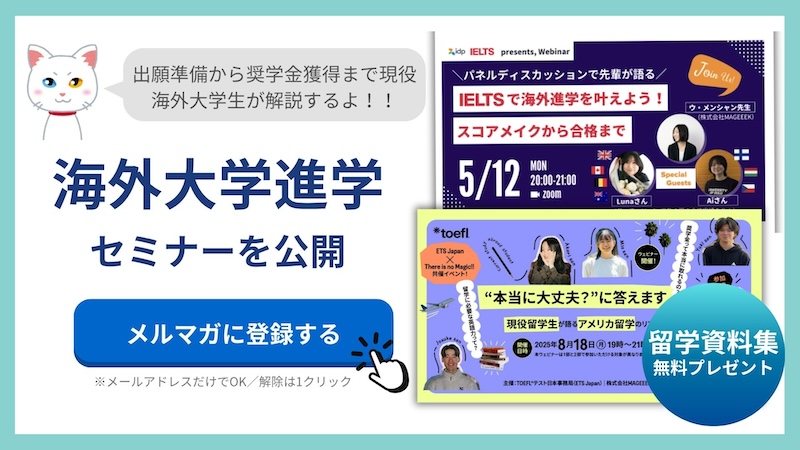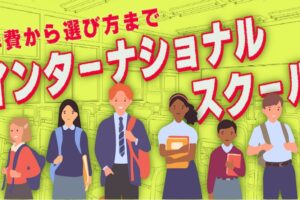まず、高校生のあなたへ。
奨学金の審査では、成績や英語スコアだけで差がつかない場面が増えています。
最後のひと押しになるのは、「なぜ海外で、なぜその分野を学ぶのか」を自分の言葉で語れるかどうか。
うわべの“憧れ”ではなく、原体験からつながる理由と、学びを未来にどう活かすか——その筋道が伝わると、読み手の心は動きます。
次に、保護者のあなたへ。
志望理由は、単なる作文ではなく、お子さんの価値観や将来像を言語化するプロセスです。
ここが整理できると、出願戦略や大学選び、家計の見通しまで、判断が一段クリアになります。
面接や推薦状の整合性も取りやすくなり、結果的にご家庭での支援や進路相談もスムーズに進められるようになります。
本記事では、財団・大学ごとの“型”から入るのではなく、自分の想いを自分の言葉で言語化するところから丁寧に進めます。
読み終えるころには、あなた自身の物語が、自然に志望理由へと形になるはずです。
目次
なぜ「留学奨学金の志望理由」が最重要なのか
多くの高校生が、奨学金の準備を始めるときにまず意識するのは「スコア」や「成績」かもしれません。
けれど実際の審査では、数字では測れない“想いの深さ”が最後の決め手になることが少なくありません。
財団や大学の選考者が知りたいのは、「なぜこの子が海外で学ぶ必要があるのか」。
その答えを自分の言葉で、筋の通ったストーリーとして語れるかどうかが、合否を分ける大きなポイントになります。
過去の合格者たちに共通するのは、成績よりもむしろ「自分の経験と将来のビジョンが一本の線でつながっている」こと。
たとえば「高校での課外活動の経験を通じて教育格差を感じた → 教育政策を学びたい → 将来は日本の地域教育に貢献したい」というように、過去・現在・未来の文脈が自然につながっている人は強い印象を残します。
海外大学の奨学金(Need-based/Merit-based)でも同じです。
選考者は、単に優秀な学生を探しているわけではなく、「何を大切に生きてきて、これからどう世界と関わろうとしているのか」という価値観や探究心、そして人としてのストーリーを見ています。
つまり、志望理由は“作文”ではなく“あなた自身を映す鏡”。
上手く書くことよりも、「自分の中の本当の理由」を掘り出し、それを誠実に伝えることが、何よりも評価されるのです。


書く前にやるべき“自己分析”3ステップ
エッセイで伝わる言葉は、自分の中から出てきた言葉だけ。
だからこそ、書き始める前に「なぜ自分はこれを学びたいのか」を整理しておくことが大切です。
この3ステップは、志望理由の土台づくりであると同時に、
奨学金の面接でどんな角度から聞かれても答えられる“思考の筋トレ”にもなります。
自分の「原体験」を掘り起こす
どんなに立派な動機も、最初は小さな感情から始まっています。
「悔しかった」「納得できなかった」「嬉しかった」——そんな心の動きが、あなたの志望理由の“核”です。
- 高校生活で最も心を動かされた出来事は?
- それはなぜ印象に残っている?(驚き・悔しさ・感動など)
- その経験を通して、自分は何を学び、どう変わった?
- その体験が、今の「興味」「関心」「価値観」にどう影響している?
- 似た経験を通じて、自分の中で一貫して大事にしている考えはある?
たとえば、部活で思い通りにいかなかった経験や、家族の一言で将来を考え始めた瞬間も立派な“原体験”です。
「誰かに言われたから」ではなく、「自分が感じたから」という動機が強さになります。
面接でもよく聞かれる「なぜその分野?」「きっかけは?」に、ストーリーを通して自然に答えられるようになります。
「なぜ海外で学びたいのか」を明確にする
多くの高校生がここでつまずきます。「英語を使いたい」「海外の方がレベルが高い」——それだけでは、説得力が弱い。
本当に大切なのは、「自分が成長するために、海外という環境がどう必要なのか」を語れることです。
- 日本の大学で同じ分野を学ぶ選択肢を、なぜ選ばなかった?
- 海外大学のどんな授業スタイル・研究環境・文化が魅力的?
- 海外で学ぶことで、自分のどんな部分を成長させたい?
- 多様な価値観に触れることで、自分の考え方はどう変わりそう?
- 留学生活で直面するであろう困難を、どう乗り越えたい?
「海外に出る理由」は華やかなものではなくていい。
「今の自分を変えたい」「違う考え方の中で挑戦してみたい」——そんな等身大の想いが、選考委員の心を動かします。
「英語で学ぶ」ではなく、「どんな環境が自分を成長させるのか」を語る。
そこに“リアルな動機”があると、書類も面接も一貫します。
将来にどうつながるのかを描く
最後は、“未来の自分”を言葉にするステップ。
ここで多くの人が、「まだ将来なんてわからない」と手が止まります。でも、完璧な計画は要りません。
いまの時点で信じている「こうありたい姿」を描くことが大事です。
- 学んだ知識・経験を、どんな形で誰に届けたい?
- 5年後・10年後、どんな人間として社会に関わっていたい?
- 留学後、どんな変化を自分や周囲にもたらしたい?
- 「成功」とは、あなたにとってどういう状態?
- あなたの価値観や人生の目標に、学びがどう結びついている?
「社会のため」ではなく、「自分の中の違和感を解決したい」でもいい。その“等身大の理想”こそが、説得力を生みます。
「財団に貢献したい」よりも、「自分の信じる社会にどう近づきたいか」を語る。
この視点は、面接の定番質問「卒業後はどうしたい?」にそのままつながります。
「なぜこの大学か」「なぜこの学びか」「どう社会に返すのか」を一貫して説明できる人は、審査でも信頼されます。
つまり、自己分析=エッセイ・面接・交渉すべての土台。
この3ステップを丁寧にやるだけで、あなたの“留学ストーリー”は驚くほど強くなります。


留学奨学金の志望理由の構成テンプレート
奨学金のエッセイを書こうとすると、「どう書けば正解なの?」「評価される文章って?」とつい形から入ってしまいますよね。
でも実際の審査で響くのは、きれいな文よりも、“その人にしか書けない物語”です。
選考委員が知りたいのは、あなたが「何を学びたいか」よりも、「なぜそう思うようになったのか」。
つまり、行動や選択の裏にある“理由”と“想い”なのです。
きっかけ(Why Me)——あなたの人生の転機・原体験
最初に思い出してほしいのは、「なぜ、今の自分がこの道を選びたいのか」。
たとえば、
- 部活で感じた挫折や悔しさ
- 家族の出来事を通して考えた社会の仕組み
- ボランティアで出会った人との会話
- ふと見たニュースに心がざわついた瞬間
「これをなんとかしたい」と思ったあの瞬間が、志望理由の出発点です。
それは大きな出来事でなくても構いません。自分が動かされた“実感”をたどることが、志望理由の原石になります。
ストーリー例①:地方の小さな学校で感じた「情報の壁」
地方の公立高校に通っていて、英語が好きでも留学情報が全く届かなかった。
「なぜ、同じ努力をしてもチャンスの量が違うんだろう?」と思ったのが始まりでした。
自分で海外大学を調べ始め、SNSで同世代の留学体験を発信。
今は後輩向けに「留学ガイド冊子」を作る活動をしています。
こうした経験から、教育格差をデータで可視化する教育政策を学びたいと思うようになりました。
➡ 特徴: “不公平感”という個人的な感情が、探究や課外活動に発展している。単なる「教育に興味がある」ではなく、体験と行動に物語がある。
ストーリー例②:母の介護を通して感じた「声なき課題」
中学の終わりから母の介護を手伝う中で、
医療スタッフとの間に“言葉の壁”を何度も感じました。
日本語でさえ伝わりにくい現場で、
外国人労働者がどうやって安心して働けるのか、疑問を持つようになりました。
そこから福祉系のNPOでボランティアを始め、
将来は多言語医療支援を仕組み化する研究をしたいと考えています。
➡ 特徴: 家庭の実体験が、社会課題の発見 → 行動 → 将来の方向性に自然につながっている。
ストーリー例③:失敗から見えた“探究の楽しさ”
理科の自由研究で、なぜか何度やっても結果が出ない。
悔しくて毎日ノートをつけているうちに、
「どうして失敗したんだろう?」を考える時間がいちばん楽しいことに気づきました。
そこから科学部でデータ分析を担当するようになり、
いまは再生可能エネルギーのミニプロジェクトを進めています。
➡ 特徴: 一見「平凡な失敗」から出発しているが、思考の深まりと行動が語られている。ストーリーの芯は“成功体験”ではなく“気づき”。
探究(Why This Field)——学びたい分野への興味と経緯
次に、「なぜその分野を学びたいのか」。ここでは“知的好奇心”を一歩深く掘る段階です。
たとえば:
- 教育格差をなくすには何が根本原因なのか?
- 環境問題にどう立ち向かう技術があるのか?
- 経済や国際関係の仕組みを、自分の目で確かめたい。
ただ「興味がある」ではなく、「この問いを解きたい」という形にできると、エッセイに芯が生まれます。
ストーリー例①:教育政策・社会学系
地元の公立中学で、英語の授業が先生によってまったく違うことに驚きました。
あるクラスでは海外ニュースを取り上げて討論しているのに、
別のクラスでは文法だけを暗記して終わってしまう。
「なぜ、同じ学校でも学びの質がこんなに違うのか?」
そう疑問に感じて、地域の教育NPOでボランティアを始めました。
活動を通じて、制度や政策が現場に与える影響を実感。
今は「教育格差をどう構造的に減らせるか」を学びたいと考えています。
➡ 具体化のポイント:「体験 → 疑問 → 行動 → 学びたい問い」という流れ。“格差”という社会的テーマが、自分の現場経験から導かれている。
ストーリー例②:環境・サステナビリティ系
小学生の頃、近所の川がゴミで汚れていたのを見て、
友達と清掃活動を始めたことがあります。
でも、どんなに片づけても数日後にはまた元通り。
「なぜ人は環境を守ろうと思っても、行動に移せないのか?」
という問いが生まれました。
高校では地学と社会科をかけ合わせて「人と環境の関係」を探究し、
今は行動科学と環境政策の両面からアプローチしたいと考えています。
➡ 具体化のポイント:単なる「環境問題に関心」ではなく、「人の行動」と「制度」の交差点に焦点を当てている。
ストーリー例③:国際関係・経済学系
ニュースで円安の話題を聞いても、周囲の大人が「よく分からない」と言っていた。
でも、自分はそれが気になって経済ニュースをノートにまとめ始めた。
為替の変動が海外留学費用や輸入物価にどう影響するのかを調べるうちに、
「経済の仕組みを理解すれば、世界の見え方が変わる」と感じた。
その後、模擬国連に参加して、政治と経済がつながる瞬間にワクワクした。
今は、国際経済を通じて“人の生活に影響を与える仕組み”を学びたいと思っている。
➡ 具体化のポイント:身近なニュース → 疑問 → 自発的な調べ → 探究活動へ。“好奇心が行動に変わった”というプロセスが伝わる。
挑戦(Why Abroad)——なぜ海外で学ぶのか
多くの高校生がここで悩みます。
「英語で学びたい」だけでは足りません。選考委員が知りたいのは、“なぜ海外でなければいけないのか”。
例:
「多様な価値観の中で自分の考えを試したい」
「教科書で学んだ理論を現場で体験したい」
「正解が一つではない議論の文化に身を置きたい」
こうした“海外でしか得られない理由”を、あなたの物語と結びつけて語ると説得力が増します。
ストーリー例①:教育×海外の現場で「多様性」を学ぶ
高校でボランティア活動をしているときに、外国にルーツを持つ子どもたちが
授業についていけずに悩んでいる姿を見ました。
「日本語を話せないだけで、能力まで評価されないのはおかしい」と感じ、
教育の多様性について興味を持ちました。
ただ、日本の学校では“標準化された教育”が中心で、
個々の違いをどう生かすかという議論が少ない。
海外では、ディスカッション形式の授業やインクルーシブ教育が進んでおり、
実際に現場でその仕組みを学びたいと思いました。
➡ ポイント:「自分の現場体験(外国ルーツの子ども)→日本の限界→海外の必然性」という流れ。“海外ならでは”の学びが自然に導かれている。
ストーリー例②:理系×実践的学びの環境を求めて
高校の理科の授業では、実験の多くがあらかじめ結果が決まっているものでした。
「なぜ失敗するのか」を考える過程こそが面白いのに、
その議論の時間がほとんどないことに物足りなさを感じました。
海外大学では、学生が自分で仮説を立て、研究計画を立てる授業が多く、
失敗も“探究の一部”として評価されると知りました。
理論だけでなく、自分の手で試しながら学びたい。
そんな学び方ができるのは、海外の研究主導の大学だと感じました。
➡ ポイント:「国内の限界 → 海外の教育文化 → 自分の探究姿勢との一致」。“失敗が評価される学び”という独自の切り口で差別化。
ストーリー例③:国際関係×多文化環境での対話
模擬国連に参加して感じたのは、国や立場によって“正解”がまったく違うということ。
日本では調和を重んじて結論を急ぐ議論が多いけれど、
海外の学生は対立を恐れず、自分の意見を根拠とともに主張していました。
「なぜその考えを持つのか」を問う対話の文化の中でこそ、
自分の思考力や価値観を試したいと感じたのです。
正解のない問いに挑み、他者とぶつかることで、
“自分の言葉で語る力”を磨きたい——これが私が海外で学びたい理由です。
➡ ポイント:単なる「国際性」ではなく、「対話の文化」という価値観で語る。抽象的な理想ではなく、実際に見た“学びの違い”が動機になっている。
適合(Why This University/Program)——大学やプログラムとのマッチング
ここでは、「その大学でなければならない理由」を明確にします。
たとえば、
- 教授や研究室が自分の関心テーマと重なっている
- 学びのスタイル(少人数制・実践型など)が自分に合っている
- 留学生が活発で、文化的背景が多様
「なんとなく海外で学びたい」ではなく、“この環境だから成長できる”という実感を伝えましょう。
面接で「他の大学ではだめなの?」と聞かれても、自分の言葉で答えられるように。
ストーリー例①:リベラルアーツで「探究の幅」を広げたいケース
高校時代、環境問題に関心を持ちながらも、社会や経済の仕組みも理解しないと解決できないと感じました。
そのため、学問の境界を越えて学べるリベラルアーツ教育に惹かれました。
たとえば、Amherst Collegeのオープンカリキュラムでは、必修がなく自分で科目を設計できます。
この自由度の中で、環境科学と行動経済学を組み合わせ、
「人が環境行動を起こす心理的要因」をテーマに探究したいと思っています。
➡ ポイント: 大学の特徴(オープンカリキュラム)が「自分の探究テーマ」とつながっている。「自由に学べる」だけでなく、「なぜ自分に合うか」を説明している。
ストーリー例②:研究大学で「理論と実践」をつなげたいケース
高校では、理科の授業で実験を通して学ぶことが好きでしたが、
日本の授業では“決まった答え”を出すことが中心でした。
一方、University of British ColumbiaのApplied Scienceプログラムでは、
学生自身が社会課題を設定してプロジェクトを進める“Design Studio”があり、
実験・失敗・改善を重ねながら理論を応用する文化が根づいています。
自分の「考えながら手を動かす学び方」が活かせる環境だと感じました。
➡ ポイント: プログラムの教育手法を理解し、自分の学習スタイルと重ねて説明している。
ストーリー例③:多文化キャンパスで「価値観の多様性」を体験したいケース
模擬国連の経験から、多様な意見が交差する場で議論することの大切さを感じました。
King’s College LondonのGlobal Politicsプログラムでは、
留学生比率が6割を超え、政治を多角的な視点から学べるのが魅力です。
「一つの正解ではなく、複数の立場を理解する力」を養えるこの環境で、
日本社会の政策立案に活かせる視座を身につけたいと思っています。
➡ ポイント: 「国際的」ではなく、“多文化の環境が自分の成長にどう影響するか”を具体化。
貢献(Impact/Future Vision)——将来の社会的意義・あなたの役割
最後は、「自分がどう生きたいか」を未来につなげる部分です。
完璧な計画を書く必要はありません。
むしろ、いまの自分の延長線上にある“リアルな仮説”を描くほうが心に響きます。
例:
「地方でもエネルギーで地域を支えられる仕組みを作りたい」
「教育機会の格差を縮める制度を設計したい」
「日本の研究を世界に発信できる橋渡し役になりたい」
ストーリー例①:地域からエネルギーを変える(理系・環境系)
東日本大震災の経験を通して、地方のエネルギー供給の脆弱さを実感しました。
将来は、再生可能エネルギーを地域の産業と結びつけ、
「地方が自立して電力を生み出せる仕組み」を作りたいと考えています。
海外では、行政・企業・研究者が協働して小規模エネルギー事業を進めており、
そうした事例を学んで日本の地域政策に応用することが目標です。
➡ ポイント: 震災という原体験→海外学びの意義→社会的ビジョンへ。「自分だから描ける未来」が具体的に見える。
ストーリー例②:教育アクセスを広げたい(社会科学系)
中学生のとき、経済的な理由で塾に通えず進路を諦めた友人がいました。
その経験がきっかけで、教育機会の不平等に関心を持ちました。
将来は、政府やNPOと連携して、家庭の所得に左右されずに学べる仕組みを作りたい。
海外の教育制度を比較しながら、「教育×テクノロジー×政策」を結びつける研究に挑戦したいです。
➡ ポイント: 個人の体験から出発し、政策・仕組みへ拡張。「誰のために何をしたいのか」が明確。
ストーリー例③:日本の研究を世界に橋渡しする(理系研究職志望)
高校のサイエンスフェアで、海外の学生たちが自信をもって自国の研究を発表している姿に刺激を受けました。
一方で、日本の高校生の多くは“英語で自分の研究を語る”機会が少ない。
将来は、日英両方の研究文化を理解したうえで、
日本の研究者が世界で発信できるような橋渡し役になりたいと考えています。
そのために、英語で科学を発信する力を海外大学で身につけたいです。
➡ ポイント: “小さな違和感”を社会的意義に転化。個人の気づきが国際的な目標に自然に接続している。
審査員は“完璧な未来像”よりも、“芯のある挑戦”を応援したいと思っています。
あなたの想いが社会のどこにつながっているかを、等身大で語ることが大切です。
志望理由は「書類」ではなく、「自分の人生のストーリー」です。
模範解答を探すより、自分の過去・今・未来を一本の線でつなぐこと。
それができれば、どんな質問にも自信を持って答えられるようになります。


財団や大学向けに“合わせていく”最後のステップ
ここまでで「自分は何を学びたいのか」「なぜ海外なのか」「どう社会に還したいのか」が整理できたら、最後のステップは——それを財団や大学のストーリーと重ねることです。
ここで意識してほしいのは、「迎合」ではなく「共鳴」。
つまり、自分を変えて相手に合わせるのではなく、自分の中にある想いと財団の理念がどこで響き合うかを探す作業です。
① 財団や大学の「言葉」を読み取る
募集要項や理念のページを読むと、どの財団も似たような言葉を使っているように見えます。
でも、よく読むと、そこには“選ぶ軸”の違いがあります。
- 柳井財団:社会貢献・地域創生など「行動で社会を変える人」を求める
- 笹川平和財団:国際理解・平和構築など「グローバルに橋をかける人」を重視
- JASSO(日本学生支援機構):誠実・継続・努力など「堅実で信頼できる挑戦者」を支援
財団の言葉を「暗記」する必要はありません。「あ、自分の想いはこの理念と近い」と感じるポイントを一つでも見つけたら、それを出発点にしましょう。
自分の“核”と重なる部分を探す
自己分析で言語化した自分のストーリーを、財団の軸とマッピングしてみます。
| あなたの軸 | 財団の軸 | 共鳴する言葉の例 |
| 教育格差をなくしたい | 笹川平和財団(国際理解) | 「学びを通して国と国の壁をなくす」 |
| 地方の再生エネルギーに貢献したい | 柳井財団(社会貢献) | 「地域の未来を自分の手で変える」 |
| 自分の努力で環境を変えたい | JASSO(堅実・努力) | 「小さな挑戦を積み重ねて未来を作る」 |
こうして書き出すと、「自分の想いが誰と共鳴するか」が明確になります。
その“重なる部分”を、エッセイや面接の中で自然に織り込みましょう。
たとえば、柳井財団なら「自分の行動が周囲を変えた瞬間」を具体的に語る。
笹川なら「異なる価値観と対話した経験」を入れる。
それだけで、あなたのストーリーは理念と“響き合う”文章に変わります。
「合わせる」ではなく「共鳴させる」
ありがちな失敗は、「財団の理念に寄せすぎる」こと。
無理に“それっぽい”ことを書くと、どこかで文章に嘘が生まれます。本当に大切なのは、あなたの物語の中にすでにある共通点を見つけることです。
選考委員は、「自分の理念を完璧に理解した人」ではなく、「同じ方向を見て歩いている人」に心を動かされます。


一人では見えない「自分の軸」を見つけるために:並走型出願サポート
ここまで読んで、「自分も自己分析をやってみよう」と思った人もいるかもしれません。
でも、正直に言うと——このステップは誰にとっても簡単ではありません。
高校生の時点で“将来何をしたいのか”を明確に語れる人なんて、ほとんどいません。大学生でも、社会人になってからでも、自分の軸を見つけるのは難しいことです。
けれど、それでも「自分は何を大切にしたいのか」を考える時間を持つこと自体が、成長の第一歩になります。
対話が「自分の言葉」を育てる
ひとりで考えていると、どうしても思考がぐるぐる回ってしまうものです。
「自分の原体験って何だろう?」「なぜそれが大事なんだろう?」
そう問い続けても、言葉にならないことは多い。だからこそ、対話が必要です。
There is no Magic!! の並走型出願サポートでは、この「対話を通じた自己分析」を最も大切にしています。
年齢の近いメンターたちが、同じように悩み、考え、乗り越えてきた経験をもとに、あなたの中の考えを少しずつ引き出していきます。
「あかりさんが内面に寄り添って話を広げてくれて、
るなさんは問いかけで思考を深掘りしてくれた。
気づいたら、自己分析が自然にできていました。」
— Parsons School of Design/Ohio Wesleyan University(5万ドル奨学金獲得) 合格者 のんさん
「メンターと話しているうちに、ぽろっと出た言葉で
“あ、自分はこうなんだ”と気づけた。」
— Grinnell College/柳井財団奨学生 Rayさん
ひとりでは気づけない「問い」に出会う時間
家族や先生には話しづらいことも、少し年上で海外進学を経験しているメンターになら、素直に話せることがあります。
「対話」こそが、自分の中の問いを見つけ、自分の言葉で語れるようになる時間です。
たとえば、SAK University(University of Essex日本提携校)に進学した受講生は、メンターとの対話を通して進路を見つめ直し、こう話してくれました。
「もし並走型を頼んでいなかったら、自分の人生をここまで真剣に考えることはなかった。」
対話を重ねるうちに、“自分は何が好きで、何に怒りや希望を感じるのか”が少しずつ言葉になっていく。
それは、たとえ今すぐ明確な答えが出なくても、「考え続ける力」を育てる貴重なプロセスなのです。
メンターと共に歩く「成長のプロセス」
並走型のメンターは答えを教えるのではなく、あなたの中にある“種”を一緒に見つけていきます。
- 自己分析で自分の価値観を整理する
- 志望理由や奨学金エッセイを形にしていく
- 留学後の人生設計まで一緒に考える
このプロセスを、複数のメンターがチームで支えるのが並走型の強みです。
視点の違う先輩たちと対話を重ねることで、思考が磨かれ、言葉が深まっていく。
志望理由を書くことも、奨学金を勝ち取ることも、すべての出発点は自己理解です。
けれど、それは「完璧な答えを出す作業」ではなく、自分と向き合い続ける旅なのです。
There is no Magic!! の並走型は、その旅をひとりで抱えないための“伴走者”です。
本音で話せる第三者と出会うことで、きっと、まだ言葉になっていない“あなたの想い”が見えてきます。

まとめ:奨学金エッセイは“自分と向き合う鏡”
奨学金エッセイを書くということは、ただ合格を目指して「正しい答え」を書く作業ではありません。
それは、自分がどんな価値観を持ち、何を大切にして生きていきたいのかを見つめ直す時間です。
つまり、志望理由とは“財団や大学のために書くもの”ではなく、自分自身と向き合うための鏡なんです。
書いていくうちに迷ったり、言葉が出なくなったりする瞬間もあると思います。
でも、その「悩む時間」こそが、あなたが本気で考えている証であり、成長のプロセスそのもの。
そして、その思考の深さは必ず文章にも滲み出ます。結果として、読む人の心を自然に動かす“共感されるエッセイ”になるのです。
奨学金の選考で評価されるのは、完璧な文章や派手な成果ではなく、「自分の言葉で語れるようになった人」。
自分の軸を見つけ、その言葉で未来を描けるようになったとき、その先にある奨学金も、留学も、きっとあなたの手の届く場所になります。