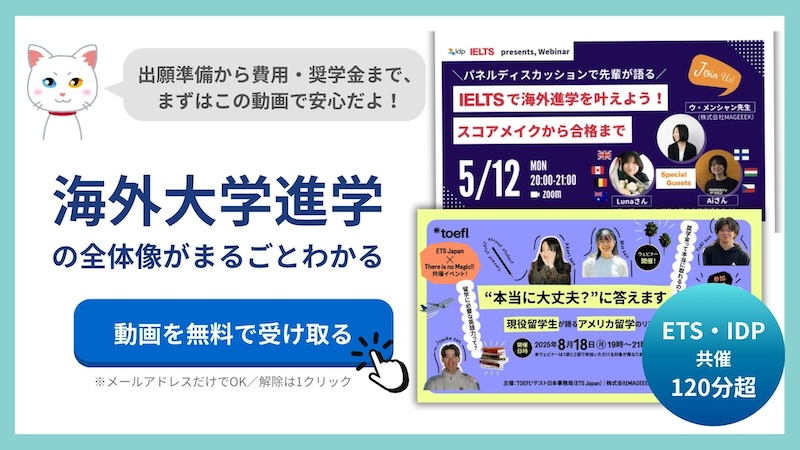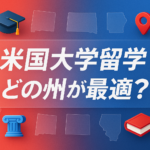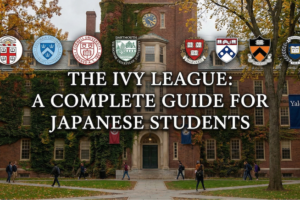アメリカの大学選びは、日本とは前提が大きく異なります。
州立・私立・リベラルアーツなど大学の種類が多く、入学基準や学費、評価方法も一律ではありません。
そのため、“名前の知れた大学を選ぶ”だけでは、自分に合った環境を見つけるのは難しいのが現実です。
この記事では、アメリカ大学選びの基本と、専攻・学費・合格可能性など「自分に合う大学」を見つけるための6つのステップをわかりやすく解説します。
高校生や保護者の方が、将来の目標に合った最適な選択ができるよう、現実的かつ具体的に整理しました。
- 結論:偏差値やランキングだけで選ぶのはNG。「自分がどんな環境で伸びるか」という価値観(Fit)を軸にするのが最大の成功法則。
- 種類:選択肢は主に4つ。少人数の「リベラルアーツ」、規模と多様性の「州立」、研究の「私立」、コスパと編入の「コミカレ」。
- 費用:学費は高いが、「奨学金」や「コミカレからの編入」を活用すれば、実質負担は日本の私大レベルまで抑えられる可能性も。
- 戦略:「挑戦校(Reach)」「実力校(Target)」「滑り止め(Safety)」の3つに分けて出願リストを作るのが鉄則。
詳しくは記事本編で徹底解説!👇
目次
アメリカ大学の選び方とは?志望校選びで大切なこと
アメリカの大学は、日本のように「偏差値」で決まる世界ではありません。
全米には4,000校以上の大学があり、それぞれが異なる教育方針や学びのスタイルを持っています。
そのため、「有名だから」「ランキングが高いから」という理由だけで選ぶと、入学後に「思っていた学び方と違う」「雰囲気が合わない」と感じることもあります。
大切なのは、数字や知名度だけで判断するのではなく、自分がどんな環境で、どんな学び方をしたいのかという価値観を軸に大学を選ぶことです。
志望校選びの出発点は「なぜアメリカで学ぶのか」
何を学びたいのか、どんな経験を積みたいのか――自分の目的が出発点になります。
まずは、「なぜアメリカで学びたいのか」を掘り下げてみましょう。
理由は立派でなくて構いません。むしろ、自分の心が動いた瞬間に目を向けることが大切です。
- 高校の英語の授業で、海外の社会問題をディスカッションした時に、もっと本音で意見を交わせる環境に憧れた
- 好きな映画監督や研究者がアメリカの大学出身で、「あんなふうに学びたい」と思った
- 進路相談で「日本ではその分野を学べる大学が少ない」と聞き、選択肢を広げたいと思った
- 家族や先生の影響で、小さい頃から海外に興味を持っていた
- 将来は海外企業や国際機関で働きたいから、学生のうちに多様な価値観に触れたい
どんな動機でも、それが“あなたがアメリカを選んだ理由”になります。
「なんとなく行きたい」ではなく、「なぜアメリカなのか」を言葉にすることが、大学選びの第一歩です。
その答えは、偏差値やランキングではなく、あなたの中にすでにあるはずです。
目的が決まると、大学のタイプは自然に絞られる
「なぜアメリカで学びたいのか」が見えてくると、次に考えるべきなのは「どんな学び方をしたいか」です。
アメリカの大学は、大学ごとに得意分野や教育スタイルが大きく異なります。
同じ「経済学」でも、理論を深く研究する大学もあれば、実践的なビジネス教育に強い大学もあります。
また、学生が専攻を自由に選び、幅広い分野を学べる「リベラルアーツ大学」と、専門を早くから深める「総合大学」でも、学び方の自由度が違います。
そのため、「どんな専攻を学びたいか」「どんな学び方をしたいか」によって、最適な大学は自然と変わってきます。
たとえば、
- 幅広く学んで自分の興味を探したい → リベラルアーツ系大学
- 研究や大学院進学を視野に入れたい → 総合大学(リサーチ型)
- 実践的なスキルを身につけたい → 都市部のビジネス系大学や工科大学
将来のキャリアがまだぼんやりしていても問題ありません。
アメリカの大学では、入学後に専攻を変更することも一般的です。
むしろ「学びながら将来を見つける」ことを前提にした教育システムなので、“現時点の興味”を出発点にするだけで十分です。


ステップ1|自分の価値観を深堀りしてみる
まずは、自分の価値観を探るために、以下のような視点から、気軽にノートに書き出すような気持ちで考えてみましょう。
ここで大切なのは、完璧な答えを出すことではありません。多くの人が、最初から明確な夢を持っているわけではないのです。
考えながら少しずつ、「何に興味があるのか」「どんな環境で学びたいのか」「どうすれば実現できるのか」が、形になっていくはずです。
興味から考える
勉強の中で楽しかった授業、夢中になれた活動、つい調べてしまうテーマ。
そうした小さな「好き」や「面白い」が、将来の専攻を選ぶヒントになります。
たとえば、
- 英語で海外のニュースを読むのが楽しい
- 美術の授業でデザインに没頭した
- 学校のディスカッションで社会問題に意見を言うのがワクワクした
どんなに漠然としていても構いません。
その“興味のかけら”を拾い集めていくことが、あなたの進む方向を照らしてくれます。
将来像から考える
「将来の夢が決まっていない」と焦る必要はありません。
大事なのは、“どんな環境で成長したいか”を思い描くことです。
たとえば、
- 多様な国の学生と本音で意見を交わしたい
- 自分のアイデアを形にできる場所で挑戦したい
- 現場で社会課題を学び、解決策を考えたい
そうしたイメージが、どの大学タイプ(州立・リベラルアーツ・私立など)が合うかを見極める軸になります。
大学は「夢を決める場所」ではなく、「夢を育てる場所」だと考えてみてください。





ステップ2|大学タイプの違いから自分に合う環境を探す
アメリカの大学は、ひとくちに「大学」と言っても、タイプによって規模も学び方もまったく異なります。
州立・私立・リベラルアーツ・コミュニティカレッジの違いを理解することで、自分に合う学習環境が見えやすくなります。
州立・私立・リベラルアーツ・コミュニティカレッジの特徴比較
まずは大学の種類ごとの特徴の違いを理解しましょう。
| タイプ | 主な特徴 | 学費の目安 |
| 州立大学(State University) | 各州の公立大学。地元の学生が多く、キャンパス規模が大きい。研究分野も幅広い。 | 留学生:約25,000〜40,000ドル/年 |
| 私立大学(Private University) | 財団や寄付で運営。学生数が少なく、サポートが手厚い。 | 約45,000〜70,000ドル/年 |
| リベラルアーツ・カレッジ(Liberal Arts College) | 人文・社会・自然科学を幅広く学ぶ小規模大学。教授との距離が近い。 | 約40,000〜60,000ドル/年 |
| コミュニティカレッジ(Community College) | 2年制の公立短期大学。英語力や費用を抑えてスタートできる。4年制大学への編入も可能。 | 約10,000〜20,000ドル/年 |
どのタイプにもメリットと課題があります。
たとえば、州立大学は規模が大きく活気に満ちていますが、クラス人数も多く、授業は自己管理が求められます。
一方、私立大学やリベラルアーツ・カレッジでは、教授との距離が近く、サポートも丁寧。ただし、学費はやや高めです。
コミュニティカレッジは、英語力や費用の面で不安がある学生が最初の2年間を過ごす選択肢として人気が高く、優秀な学生はその後名門大学に編入するケースも珍しくありません。
どんな学生にどのタイプが向いているか
アメリカでは「どこに受かるか」よりも「どんな環境で伸びるか」が重視されます。
自分の性格や学び方に合わせて、どんな大学タイプが合いそうかを考えてみましょう。
州立大学が向いている人
- 活気あるキャンパスで多様な学生と関わりたい
- 幅広い専攻から柔軟に選びたい
- 比較的コストを抑えて学びたい
→ 例:カリフォルニア大学群(UC系)は世界的にも評価が高く、研究と実践のバランスが取れた環境。
私立大学が向いている人
- 教授との距離が近い環境で学びたい
- 学生支援やキャリアサポートを重視したい
- 成績・エッセイで奨学金を狙いたい
→ 例:ボストン大学やNYUなどは、都市型で学びながら就職準備も進めやすい。
リベラルアーツ・カレッジが向いている人
- 一つの分野に縛られず、幅広く学びたい
- 少人数で深い議論やディスカッションが好き
- 「考える力」「伝える力」を伸ばしたい
→ 例:Amherst CollegeやWilliams Collegeは、教授との距離が非常に近く、大学院進学率も高い。
コミュニティカレッジが向いている人
- 費用を抑えてアメリカの教育に慣れたい
- 英語力を伸ばしながら進学準備をしたい
- 名門4年制大学への編入を目指したい
→ 例:Santa Monica CollegeやDe Anza Collegeは、UCLAやUC Berkeleyへの編入実績が豊富。
タイプと立地の関係(都市型大学と地方大学の違い)
大学のタイプは、立地によっても学び方や生活の雰囲気が変わります。
特にアメリカは国土が広く、都市と地方の差が大きいのが特徴です。
都市型の大学(New York・Los Angelesなど)
- インターンやアルバイトなど、実践のチャンスが多い
- カフェや交通機関など生活の利便性が高い
- 一方で、家賃や生活費は高く、人の入れ替わりが早い環境
→ 社会に近い刺激的な環境を求める学生に向いています。
地方型の大学(中西部・南部・郊外など)
- 落ち着いたキャンパスで、勉強や研究に集中できる
- 家賃や物価が安く、生活コストを抑えやすい
- 学生同士のつながりが深く、アットホームな雰囲気
→ 静かな環境で腰を据えて学びたい学生に向いています。
たとえば、州立大学は地方にキャンパスを持つことが多く、生活費を抑えやすいのが魅力。
一方、私立大学は都市部に位置するケースが多く、企業との距離が近いため、キャリア志向の学生には都市型が人気です。
どちらが「良い・悪い」ではなく、自分がどんな生活を送りたいかをイメージして選ぶことが大切です。


ステップ3|学費と奨学金から現実を把握する
アメリカの大学進学を考えるとき、多くの人が最初に不安を感じるのが「費用」ではないでしょうか。
実際、アメリカの大学の学費は世界でも高水準で、数字だけを見ると「そんなにかかるの?」と驚くかもしれません。
ただし重要なのは、「全額を自費で払う」前提で考える必要はないという点です。
実際には、多くの留学生が奨学金や学費免除制度を活用し、負担を大きく抑えて進学しています。
つまり、考えるべきなのは「払えるかどうか」ではなく「どんな形でサポートを得られるか」です。
学費と生活費の相場を理解しよう
アメリカの大学の学費は大学タイプや専攻、立地によって大きく異なりますが、おおよそ年間で40,000〜80,000ドル(約600万〜1,200万円)が目安です。
- 州立大学:25,000〜40,000ドル前後(寮費・生活費別)
- 私立大学:45,000〜70,000ドル前後
- リベラルアーツ・カレッジ:40,000〜60,000ドル前後
- コミュニティカレッジ:10,000〜20,000ドル程度
さらに、寮費や食費、教材費、保険などの生活費が年間15,000〜20,000ドルほどかかります。
留学生が知っておきたい奨学金の仕組みと種類
アメリカの大学は、奨学金制度が非常に柔軟で、海外大学の中でも留学生への門戸が広いのが特徴です。
しかも、大学自体が授業料の一部を免除してくれるケースが多いため、チャンスは想像以上にあります。
奨学金には主に3つのタイプがあります。
① 大学独自の奨学金
アメリカの大学では、大学独自の奨学金としてMerit-based(実績評価型)とNeed-based(経済状況考慮型)の2種類があります。
Merit-based は、成績や課外活動、エッセイなどをもとに出願時に自動的に審査される大学も多く、優秀な留学生には授業料の半額〜全額免除が与えられることもあります。
一方、Need-based は、家庭の収入や資産状況をもとに「どれだけ経済的な支援が必要か」を考慮して支給される奨学金です。
大学によっては、合格後にこれらを含む学費・奨学金条件(financial aid package)の再審査や調整をお願いできる場合もあります。
② 日本の公的・民間奨学金
日本政府や財団が提供する留学支援制度も豊富です。
返済不要の給付型も多く、学費だけでなく生活費までカバーできる奨学金もあります。
③ 国際機関や海外財団の奨学金
Fulbright ProgramやJoint Japan/World Bank Scholarshipなど、分野や目的別に支援を行う奨学金もあります。
専門分野を明確にしている学生には、こうしたプログラムが強力なサポートになります。


奨学金を前提にした「複数シナリオ」で考える
留学の現実を見据えるうえで、最初にやるべきことは「家族でお金の話をする」ことです。
夢や志望校を話す前に、まず「年間でどのくらい負担できるのか」を親子で共有しておきましょう。
アメリカ大学の学費や生活費は、学校によって年間数百万円単位で差があります。
そこで、現実的な選択肢を整理するために、次のような“複数シナリオ”を考えておくのがおすすめです。
① 大学からの奨学金(学費免除)で行ける場合
成績や活動実績が高く評価されれば、大学側から授業料の一部または全額免除を受けられることがあります。
この場合、親からの支援で生活費をカバーできれば、留学を現実的に実現できます。
② 財団や外部奨学金を得て行ける場合
大学の奨学金だけでは足りない場合、日本の財団や国際機関からの支援を組み合わせるパターンもあります。
「柳井正財団」「笹川平和財団」などは、学費・生活費の全額をカバーする給付型奨学金を提供しています。
このような奨学金が取れれば、家庭の負担を最小限に抑えながら留学が可能です。
③ 奨学金が得られなかった場合の選択肢
もし大学・財団の奨学金がどちらも得られなかった場合、無理に高額な大学へ進学する必要はありません。
- コミュニティカレッジからスタートして4年制大学へ編入する
- 費用の安いヨーロッパやアジアの大学を検討する
- いったん日本の大学に進学してから交換留学や大学院で再挑戦する
など、経済状況に合わせて複数の道を描くことが大切です。
このように、「奨学金が取れたらA大学」「部分的に取れたらB大学」「取れなければ国内または他国の大学」というように、3段階の進路プランを整理しておくと安心です。
どのシナリオになっても、「行きたい」という気持ちを実現するルートが残る――それが“現実的に夢をつなぐ方法”です。
いったん日本の大学に進学してから交換留学や大学院で再挑戦するなど、経済状況に合わせて複数の道を描くことが大切です。


ステップ4|合格可能性から志望校リストを設計する
アメリカ大学の出願では、「行きたい大学」だけでなく、合格の可能性を踏まえた現実的なリスト設計が欠かせません。
志望校は「リーチ校・ターゲット校・セーフ校」の3つに分け、挑戦と安心のバランスを取ることが成功のカギになります。
志望校は3タイプに分けて考える(リーチ・ターゲット・セーフ)
出願校は、一般的に次の3タイプに分けて考えます。
リーチ校(Reach School)
難易度が高く、合格できたら夢が叶う大学。
合格率20%以下、または自分の成績より少し上のレベルの大学が目安です。
ターゲット校(Target School)
自分のGPA・スコアと合格者の平均が同程度の大学。
努力次第で十分合格が狙える現実的なラインです。
セーフ校(Safety School)
合格可能性が高く、確実に進学できる大学。
合格率が高く、英語スコア・GPAが平均より上回っている大学が目安です。
理想は、リーチ校2〜3校、ターゲット校3〜4校、セーフ校1〜2校ほどのバランス。
このようにリストを作ることで、挑戦と安心の両方を確保できます。
英語スコア・GPAから合格ラインを見極める
合格の可否を左右するのが、英語スコア(TOEFL/IELTS)とGPA(高校の成績)です。
もちろん大学によって求められる水準は異なりますが、目安を知っておくと、自分がどのレベルの大学を狙えるかが見えてきます。
| 難易度レベル | TOEFL iBT目安 | IELTS目安 | GPA目安(4.0換算) | 大学の傾向 |
| 上位校 | 100点以上 | 7.0以上 | 3.8〜4.0 | 名門私立・州立大(UC系、アイビーリーグなど) |
| 中堅校 | 80〜95点 | 6.5〜7.0 | 3.3〜3.7 | 留学生が多くサポート体制が充実 |
| 進学しやすい校 | 61〜79点 | 6.0〜6.5 | 2.8〜3.2 | 州立大やコミュニティカレッジなど |
大学によっては、TOEFLやSATを提出しなくても出願できる「テストオプショナル制度」も導入されています。
ただし、スコアを提出する方が奨学金審査で有利になる場合もあるため、できるだけ英語力を示せる準備をしておくのが安全です。
また、GPAが少し足りなくても、エッセイや課外活動、推薦状で評価されるケースもあります。
アメリカの大学は「数字だけで判断しない」文化があり、努力や個性をアピールできる余地があるのが特徴です。



ステップ5|立地・環境を「補助軸」として考える
アメリカ大学選びでは、立地は「決め手」ではなく「補助軸」です。
専攻や学び方を優先したうえで、生活や将来に影響する立地要素を確認するのが現実的です。
立地は「補助軸」として考えるのが基本
大学選びで「どこの街にあるか」を最初の判断基準にする人は少ないかもしれません。
実際、アメリカでは「何を学ぶか」「どんな学び方をしたいか」のほうが圧倒的に重要で、立地はあくまで“補助的な要素”です。
多くの学生は、専攻や教育内容を基準に大学を選び、結果として立地が決まる形になります。
たとえば、「映画を学びたいからロサンゼルス周辺」「ビジネスを学びたいからニューヨーク近郊」といったように、学びの延長線上に立地がついてくるのです。
とはいえ、立地は「直接の決め手」ではないにしても、日常生活や将来のチャンスに間接的な影響を与える要素です。
だからこそ、“行きたい大学”が見えてきた段階で、立地についても現実的に考えてみましょう。
立地を見るときに確認したい4つの視点(治安・気候・交通・生活費)
アメリカは国土が広く、州や都市によって環境がまったく異なります。
立地の違いは、学びのスタイルだけでなく、生活のしやすさや精神的な余裕にも影響します。
検討時に意識しておきたいのは、次の4つです。
① 治安
大学周辺の治安は最重要ポイントです。
大学のキャンパス自体は安全でも、夜間の外出や交通機関の利用でリスクがある地域もあります。
大学サイトや現地学生の口コミ、留学エージェントの情報などで、「キャンパスの外が安全かどうか」も確認しておきましょう。
② 気候
アメリカは、南部の温暖な地域(フロリダ・カリフォルニア)から北部の寒冷地(ミネソタ・マサチューセッツ)まで多様です。
寒暖差が激しい地域では、冬の外出や移動が制限されることもあり、気候の合う場所を選ぶだけでも生活の満足度は大きく変わります。
③ 交通アクセス
車社会の地域も多く、公共交通が整っていない大学では、車を所有する必要がある場合も。
一方、ニューヨークやボストンなどの都市部では交通機関が発達しており、移動しやすい代わりに生活費は高めです。
「留学生が移動しやすい環境か」という視点で見ておくと安心です。
④ 生活費
同じ州内でも都市と郊外では物価が倍近く違うこともあります。
家賃や食費は都市部で高く、地方は安い傾向がありますが、都市部ではインターンやアルバイトの機会が多いという利点も。
「費用を抑えたい」だけでなく、「機会を得たい」という視点で、バランスを取るのがポイントです。
学びを最大化する「専攻×立地」の考え方
立地を“学びを支える要素”として考えると、より現実的で戦略的な大学選びができます。
次のように、専攻と地域産業の強みを組み合わせて考えるのが効果的です。
- 映画・映像・メディア系 × カリフォルニア州(LA)
ハリウッドを中心に映像産業が集まり、インターンのチャンスも豊富。
実践的に学びたい学生にとって、現場に近い環境が大きな強みになります。
- ビジネス・経済系 × ニューヨーク州
金融・広告・コンサルなどの企業が集まり、就職機会やネットワーキングが盛ん。
都市型の大学は、授業外での学びも多く得られます。
- 工学・IT・スタートアップ系 × 西海岸(シリコンバレー・シアトル)
GoogleやMicrosoftなどの企業が集中するエリアで、大学と企業の共同研究も盛ん。
実践的なスキルを磨きたい学生にとって理想的な環境です。
- 国際関係・社会科学系 × ワシントンD.C.エリア
政府機関や国際NGOが多く、現地でのボランティアや研修の機会が豊富。
社会問題を現場で学びたい学生にはぴったりです。
このように、「専攻×立地」で考えると、大学選びが“自分の未来につながる選択”に変わります。
単に「どこで学ぶか」ではなく、「その場所でどんな経験ができるか」を意識することが、アメリカ留学をより意味あるものにしてくれます。



ステップ6|情報収集と比較の仕方
アメリカ大学選びでは、ランキングや公式サイト、体験談など、信頼できる情報源をうまく活用して、大学を比較していきましょう。
大切なのは、情報を集めすぎることではなく、自分の目的に合った視点で整理することです。
ランキングの正しい使い方(総合 vs 専攻別)
「アメリカ大学ランキング」と検索すると、数えきれないほどの情報が出てきます。
しかし、ランキングの数字だけを基準に大学を選ぶのは危険です。
なぜなら、ランキングは評価基準(研究費、卒業率、教授数など)が大学ごとに異なり、“自分にとっての良い大学”とは必ずしも一致しないからです。
アメリカでは、次の2つのランキングを区別して見るのが基本です。
総合ランキング(National Ranking)
大学全体の教育水準・施設・卒業率などを総合的に評価したもの。
例:Harvard、Stanford、MITなどが常に上位。
ただし、大学全体の規模や研究力を示すもので、学部レベルの特徴までは見えにくい。
専攻別ランキング(Major Ranking / Subject Ranking)
学問分野ごとの評価。たとえば「経済学」「心理学」「Film Studies」など。
大学によっては総合順位は中堅でも、特定の専攻分野で世界トップレベルということもあります。
大学選びでは、「自分の専攻分野+教育環境」を軸にランキングを参考にするのがおすすめです。
総合順位にとらわれず、「自分が学びたいことを一番よく学べる場所はどこか?」という視点で見ることが大切です。
公式サイト・パンフレット・バーチャルツアーの活用法
大学の雰囲気やカリキュラムを知るためには、公式情報を確認することが一番確実です。
特に海外大学は、サイトや資料が充実しており、以下のような情報を細かくチェックできます。
① 公式サイト(University Website)
- 専攻一覧・コース内容・卒業要件
- 出願条件(必要スコア・提出書類・締切)
- 奨学金情報・留学生向けサポート
英語が難しく感じても、「Admissions」や「International Students」のページを中心に見ればOKです。
大学ごとに出願要件が違うので、ここでの確認が最も重要です。
② パンフレット・カタログ(Course Catalogue)
大学が発行する公式パンフレットでは、授業の構成や教授陣、学部の特色などが詳しく紹介されています。
興味のある専攻を見比べながら、「どの大学が自分の興味を一番伸ばせそうか」を整理してみましょう。
③ バーチャルキャンパスツアー(Virtual Tour)
最近は多くの大学がオンラインでキャンパス見学を提供しています。
実際に歩いているような360°映像で、寮や図書館、街の雰囲気まで確認できます。
「海外の大学生活」をよりリアルに想像できる貴重な機会です。
現役留学生の体験談・SNS・大学フェアを活かす
公式情報だけではわからない“リアルな雰囲気”を知るには、現役学生や卒業生の声が欠かせません。
特に初めての留学を考える高校生にとって、実際にその大学に通う日本人や留学生の話は何より参考になります。
① 現役留学生・卒業生の体験談を読む
ブログやインタビュー記事では、授業の様子、寮生活、文化の違いなどが具体的に語られています。
「想像していたより課題が多い」「リベラルアーツは本当に自由だった」など、良い面も大変な面も含めて知ることができるのが利点です。
② SNSをフォローする
InstagramやYouTubeでは、大学公式アカウントや学生アンバサダーが日常を発信しています。
講義風景やクラブ活動、キャンパスイベントなどを見れば、“自分が通う姿”を想像しやすくなります。
③ 大学フェア・説明会に参加する
秋から冬にかけて、アメリカ大学の担当者が日本で説明会(大学フェア)を開催します。
担当者と直接話せる貴重な機会で、英語力が多少不安でもOK。
質問例としては、
- 留学生の割合やサポート体制
- 奨学金の有無
- 現地の生活環境や寮の雰囲気
など、ネットでは拾えない情報を得るチャンスです。
情報を集めるときに大切なのは、「完璧に比較しよう」としないこと。
すべての情報を追うのではなく、
「自分の目的に合っているか」
「自分がその環境で成長できそうか」
という軸を持って整理することです。
たとえ迷いながらでも、ひとつずつ情報を確かめていけば、必ず“自分に合う大学”の輪郭が見えてきます。
大学選びは情報の多さよりも、“自分の中で納得できる選択”を作る過程なのです。



There is no Magic!!の並走型出願サポートに相談しよう


アメリカ大学への進学は、単なる「志望校選び」ではなく、自分の生き方を探す旅です。
何を学びたいのか、どんな未来を描きたいのか――その答えを見つけるまでの道のりには、迷いや葛藤がつきものです。
費用の不安や、思うようにスコアが伸びない焦り。
周りと比べて「自分だけ遅れている気がする」瞬間もあるかもしれません。
でも、その過程こそが、自分の軸を見つける大切な時間です。
There is no Magic!! の「並走型・海外大学出願サポート」では、海外大学や奨学金を経験した先輩たちが、あなたと同じ目線で並走します。
出願書類の準備やエッセイの添削だけでなく、「なぜこの大学を目指したいのか」「どうやって自分の言葉で伝えるか」まで、対話を重ねながら一緒に整理していきます。
ときには思い描いた通りに進まないこともあります。
でも、私たちは知っています。大切なのは、進んだ道を“正解”にしていく力を育てること。
その力こそが、留学の先にある学びや人生を支えてくれます。
もし今、迷いながらも前に進みたいと思っているなら――
一度、話してみませんか?
あなたの中にある「まだ言葉になっていない思い」を、一緒に形にしていきましょう。

まとめ|「有名校」より「自分に合う大学」を選ぶ
アメリカ大学選びで大切なのは、名前よりも“自分に合う環境”を見つけることです。
どんなに有名な大学でも、目的や学び方が合わなければ充実した留学生活にはつながりません。
学びたいこと、実現したい将来像、そして費用などの現実――。
この「目的」と「現実」のバランスを考えながら、自分にとって最適な選択肢を探すことが大切です。
奨学金を利用したり、コミュニティカレッジから編入したりと、道はいくつもあります。
大学選びは、他人と比べるものではなく、自分の未来をつくる時間です。
早めの準備と情報収集から、一歩ずつ自分らしい留学の形を描いていきましょう。
アメリカ大学留学に興味を持ったなら、知っておきたい基礎知識から準備のすべてをまとめた「アメリカ大学留学完全ガイド」もあわせて読んでみてください。
皆さんの留学への最初の一歩を踏み出すきっかけになればうれしいです。
- アメリカ大学の人気専攻は?
将来を見据えた専攻選びのヒントに。アメリカで人気の専攻や専攻選びのコツを解説 - アメリカ大学留学におすすめの州は?
生活環境や費用など、「大学名」だけでは見えにくい、州ごとの特徴と選び方 - アメリカの大学の偏差値は?
「偏差値」がないアメリカでは難易度をどう測る?大学タイプ別の難易度を解説 - アメリカ大学の合格率は?
合格率が高い大学・低い大学は?「合格率」を正しく理解して戦略的に志望校を選ぼう