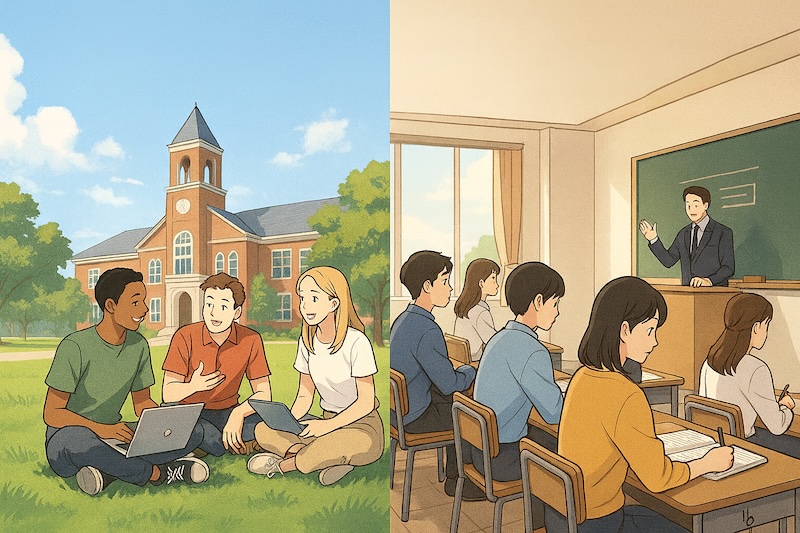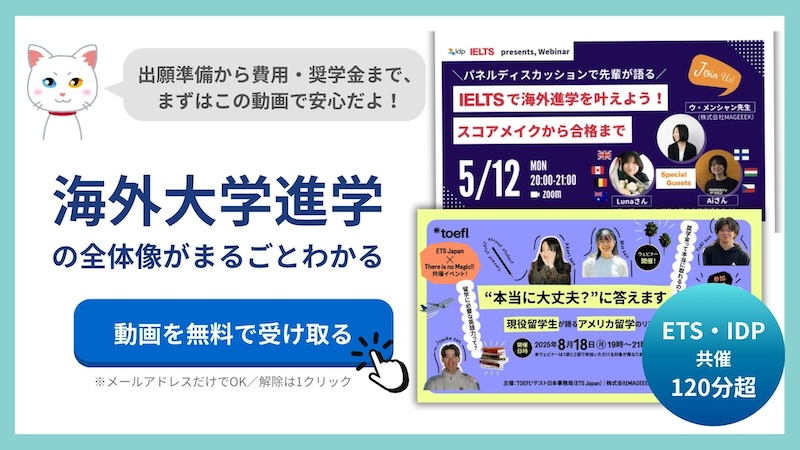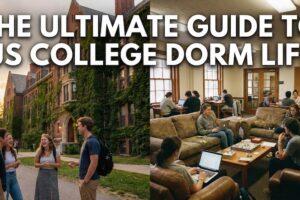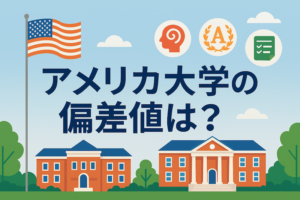日本とアメリカの大学では、入試制度から授業スタイル、学費の仕組み、卒業後のキャリアに至るまで、大きく異なる点がたくさんあります。
しかも、その違いが進学後の学びや将来の選択肢に直結するからこそ、「よくわからないまま決める」のは避けたいところです。
この記事では、以下のようなポイントをわかりやすく解説していきます。
- 入試制度や評価のされ方の違い
- 授業スタイルや専攻の自由度など、大学での学び方の違い
- 学費・奨学金制度の仕組みと費用感
- 卒業後のキャリアや就職活動の進め方の違い
高校生のあなたにとっても、お子さんの進路を考える保護者の方にとっても、「自分に合った進路選び」のヒントが見つかる内容になっています。
日本とアメリカ、どちらが良いかではなく、「どちらが自分に合っているか」を一緒に考えていきましょう。
目次
【違い①】入試制度・審査方法
日本の大学入試は「学力テストで一発勝負」、アメリカの大学入試は「高校生活全体を通じた総合評価」が基本です。
試験の得点だけで判断される日本に対し、アメリカでは勉強・活動・人柄など、多面的な努力が評価されます。
| 日本の大学 | アメリカの大学 | |
| 評価の軸 | 試験の点数(共通テスト+二次) | 高校の成績・エッセイ・課外活動など総合 |
| 失敗のリスク | 一度の試験で合否が決まる | 様々な要素でリカバリー可能 |
| 準備期間 | 高3で追い込みが中心 | 高1〜2からの積み重ねが重要 |
日本:学力試験で一発勝負
日本の大学入試は「共通テスト」+「二次試験」の得点で合否が決まります。
高校3年で集中的に受験勉強を行い、当日の得点がほぼすべてを左右するため、一度の失敗が大きく響きます。
この「一発勝負型」の仕組みが、日本の受験の緊張感を生み出しているとも言えるでしょう。
アメリカ:多面的な「総合評価」で判断
アメリカの大学入試は、Holistic Review(総合評価型選抜)を採用しています。
高校の成績(GPA)、エッセイ、課外活動、推薦状、英語試験(TOEFL/IELTS)などを総合的に評価し、学力以外の面も重視します。
つまり、「どんな経験をしてきたか」「どう成長してきたか」を通して、“人としての全体像”が見られるのです。
また、この仕組みでは高校1年生のころからの積み重ねが重要になります。
日々の成績や活動の成果がすべて出願時に反映されるため、短期的な追い込みよりも、長期的に自分の関心や努力を形にしていく姿勢が求められます。




【違い②】出願・入学時期の柔軟性
日本の大学は年1回の一斉入試ですが、アメリカの大学は出願時期や入学時期が複数あり、人によって進学スケジュールが異なります。
出願・入学タイミングを自分で決められる“自由度の高さ”が特徴です。
| 日本の大学 | アメリカの大学 | |
| 受験時期 | 年1回・一斉入試 | 通年で柔軟 |
| 入学時期 | 4月入学が基本 | 秋・春・夏入学の選択可 |
日本:一斉入試で4月に全員がスタート
日本では、大学入試は1〜2月に集中し、合格発表後の4月に全国一斉で入学します。
多くの学生が同じ時期に受験・入学するためスケジュールは分かりやすい反面、時期をずらしての進学はほぼできません。
アメリカ:入学時期を自由に選べる
アメリカの大学の出願時期・入学時期は、自由に選べるのが特徴。
最も一般的なのは9月(秋学期)入学ですが、大学によっては1月(春学期)や5月(夏学期)の入学枠も設けられています。
例えば、TOEFLやSATのスコア提出が間に合わない場合は春入学を選んだり、卒業後に少し時間を取って準備したい人は夏入学を選ぶなど、自分のペースに合わせてスケジュールを設計することが可能です。
人によって進学のタイミングが異なるため、日本のような「入学式」は基本的にありません。


【違い③】学び方・授業スタイル
日本の大学は講義中心で試験重視、アメリカの大学はディスカッションや課題中心で「参加」と「発言」が評価の軸になります。
| 日本の大学 | アメリカの大学 | |
| 授業形式 | 講義中心(受け身) | ディスカッション・実践重視 |
| 評価方法 | 試験・出席中心 | 発言・課題・総合評価(GPA) |
| 教授との関係 | 一方向の講義が中心 | 双方向・フラットな対話が基本 |
日本:講義中心で「知識を受け取る」スタイル
日本の大学では、先生が一方的に話す「講義形式」の授業が主流です。
学生はそれを聞いてメモを取り、テストやレポートで成果を評価される、という流れが一般的です。
- 1つの教室に多人数が集まり、黙って聞くスタイルが基本
- 質問や意見交換の機会は限られがち
- 成績評価は期末試験や出席による比重が高い
もちろん最近ではアクティブラーニングを取り入れる大学も増えてきましたが、全体としてはまだ「受け身型」の学習スタイルが根強く残っています。
アメリカ:議論・探究・実践の「参加型授業」
アメリカの大学では、「自分の意見を持ち、それを表現する」ことが重視されます。
授業の多くはディスカッション形式やグループワークで進められ、知識を覚えるだけでなく、“どう考えるか・どう活かすか”が問われます。
- 毎回の授業で「読んでくること」「考えてくること」が求められる
- 発言・質問・ペアワークが活発で、沈黙はNGとされることも
- 論文やプレゼンでのアウトプットが成績に大きく影響
こうした授業スタイルは「アクティブラーニング」と呼ばれ、学生の思考力・批判的視点・表現力を鍛える場として機能しています。
GPA制度で日々の積み重ねを総合的に評価
また、アメリカでは試験の点数だけでなく、授業態度・発言・課題提出などを総合的に評価する「GPA制度」が採用されています。
- 各授業の成績は「A〜F」で評価され、数値化(例:A=4.0)
- 全体の平均が「GPA(Grade Point Average)」として残る
- 就職・大学院進学・奨学金にも大きく影響
つまり、一度の試験よりも日々の積み重ねが評価される仕組みです。学生には継続的な努力と主体的な学びの姿勢が求められます。
教授はフラットな対話をする「伴走者」
アメリカの大学では、教授は「教える人」ではなく、“対話する研究者”や“知的な伴走者”として学生と関わります。
授業内外での議論やフィードバックが重視され、学生はオフィスアワー(相談時間)を活用して教授と1対1で議論するのが一般的です。
学生の意見を尊重しながら学びを共に深める、このフラットな関係が自主性を引き出す土台になっています。
対照的に、日本の大学では「先生=指導者」「学生=受講者」という構図が今も根強く残っています。
この違いが、授業への関わり方や学びの姿勢に大きな差を生み出しています。


【違い④】専攻選択の柔軟性
日本の大学は入学時に専攻が決まり、変更が難しいのに対し、アメリカの大学では入学後に幅広く学びながら専攻を柔軟に選べます。
“迷いながら進む”ことが許される仕組みで、学生一人ひとりが学びをデザインする文化が根付いています。
| 日本の大学 | アメリカの大学 | |
| 教養教育 | 学部・専攻に即した学び | リベラルアーツで幅広く学ぶ |
| 履修制度 | 専攻変更は難しい | 専攻変更・ダブルメジャーも可能 |
| 授業設計 | カリキュラムに沿って時間割を組む | 自分で履修計画を立て、時間割を設計する |
日本:専攻は固定、学びは専門中心
日本では、大学入学と同時に専攻が決まるのが一般的です。
そのため、入学前から将来の方向性を定めておく必要があり、学びは比較的早い段階で専門特化型になります。
途中での専攻変更は制度上難しいことが多く、学部の枠を超えた学びには制限があります。
アメリカ:幅広く学び、専攻は柔軟に変更可能
アメリカの大学では、多くの学生が「専攻(メジャー)」を入学時に確定していません。
1〜2年目は一般教養(リベラルアーツ)を幅広く学びながら、自分に合う分野を見つけていくのが一般的です。
例えば、心理学を専攻しようとしている学生が、哲学や統計、コンピュータサイエンス、演劇なども学ぶことで、より深く自分の関心や強みを見つけていきます。
“迷いながら進む”ことが許される仕組みだと言えるでしょう。
途中で専攻を変更したり、2つの専攻(ダブルメジャー)や副専攻(マイナー)を組み合わせて学んだりすることも一般的です。
アメリカの大学は授業設計・管理も「自己責任」
アメリカの大学では、履修登録や時間割の管理も学生自身が行います。
どの授業をいつ取るか、どの教授の授業を受けるかまで、自分で設計する仕組みです。
学期ごとの履修数や難易度の調整も自由で、早期卒業を目指すことも、ゆっくり学びを深めることも可能。
つまり、アメリカでは大学卒業までの期間も人それぞれなのです。
こうした「自分で学びをデザインする」文化が、学生の主体性や自己管理力を育てる基盤になっています。


【違い⑤】学費と奨学金制度
日本は学費が比較的安価な一方で、奨学金は返済が必要な「貸与型」が中心です。
一方で、アメリカの大学の学費は高額ですが、実際は奨学金制度が非常に充実しており、“そのまま全額を払って進学する”ケースは多くありません。
| 日本の大学 | アメリカの大学 | |
| 学費 | 比較的安価(国公立〜私立) | 高額(ただし奨学金で減額可能) |
| 奨学金 | 貸与型中心(返済あり) | 給付型が豊富(返済不要) |
| 奨学金付与対象 | 主に家計基準 | 家計+人物評価(成績・活動など) |
| キャリアへの投資回収 | 日本就職が前提 | 日本+海外キャリアでリターン可能 |
日本:比較的安価でシンプル、奨学金は「借りる」もの
日本の大学は、国公立か私立かによって学費が大きく異なります。
- 国公立大学:年間約50〜60万円(授業料のみ)
- 私立大学(文系):年間約100〜130万円
- 私立大学(理系・医療系):年間150万円〜数百万円も
日本では奨学金制度は整っていますが、その多くは「貸与型(=将来返す必要がある)」です。
給付型の奨学金も徐々に増えていますが、まだまだ競争倍率が高く、枠も限られています。
アメリカ:学費は高額、でも奨学金は「給付型」が基本
アメリカの大学の定価(Sticker Price)は高額で、以下のような費用感が一般的です。
- 私立大学:年間約500〜800万円(授業料・寮費・生活費込み)
- 州立大学(州外生):年間約400〜600万円
- コミュニティカレッジ:年間約150〜300万円程度
しかしここで重要なのは、多くの学生がこの「定価」をそのまま払っていないということ。
アメリカの大学の返済不要の給付型奨学金は非常に充実しており、うまく活用すれば実質負担を大きく減らすことができます。
- Need-based(家計基準):
世帯年収が一定以下の学生が対象。アメリカのトップ大学(ハーバードやMITなど)では、年収800万円未満で学費免除のケースも。 - Merit-based(成績・活動基準):
成績優秀者やリーダーシップを示した学生に支給。入学時に自動的に授与されるケースもあります。
こうした奨学金を活用すれば、私立大学でも実質負担が年間100〜300万円程度になることが多く、出願戦略によっては全額奨学金を得ることも可能です。
さらに、アメリカ進学は将来のキャリアという観点でも費用以上の価値があります。
卒業後はOPT(最長3年の就労ビザ)を活用して現地就職が可能で、「英語力+専攻+実務経験」は日本国内でも高く評価される傾向にあります。
つまり、アメリカ進学は高額でも“投資としてのリターンが見込める”学びなのです。






【違い⑥】キャンパスライフ・大学文化
アメリカの大学は「学ぶ場所」であると同時に「生活の場」でもあり、寮生活を中心とした一体感のあるコミュニティと、学びにつながる課外活動文化が特徴です。
| 日本の大学 | アメリカの大学 | |
| 住環境 | 自宅通学や一人暮らしが中心 | 寮生活が主流(特に1年目) |
| コミュニティ | サークルなど個人の選択による | 大学全体での一体感・つながりが強い |
| 課外活動 | 趣味・仲間づくりの側面が強い | 学び・評価・キャリアにも直結 |
日本:個人単位の生活スタイルが中心
日本の大学では、自宅通学や一人暮らしの学生が多く、生活の中心は大学外にあります。
サークルやアルバイトを通じて友人関係を築くことが多いものの、大学全体での一体感は比較的薄い傾向にあります。
また、課外活動は「趣味」や「息抜き」としての側面が強く、学業や将来のキャリアと直接結びつくことはあまりありません。
アメリカ:寮を拠点にした「共同体」としての大学生活
アメリカの大学では、1年生の寮生活が基本で、多くの学生がキャンパス内で暮らします。
食事・勉強・リラックスのすべてを同じ環境で共有し、大学が「生活の拠点」となります。
RA(寮長)やメンター制度など、上級生が下級生を支える仕組みも整っており、学年や専攻を越えた人間関係が自然に生まれます。
こうした密なコミュニティの中で、学生は協働・対話・多様性を学びながら成長していきます。
課外活動も「学び」として評価される
アメリカの大学では、課外活動やボランティアが教育の一部として重視されます。
スポーツ、文化系、地域活動、学生団体など100以上のクラブを持つ大学もあり、イベント運営やリーダーシップの経験は履歴書や推薦状にも反映されます。
社会貢献活動を通じて企業や地域と関わる機会も多く、こうした経験が将来のキャリア形成にも直結します。



【違い⑦】卒業後の進路とキャリア支援の違い
アメリカの大学は、在学中から実務経験を積み、個々のペースでキャリアを築く文化が根付いています。
日本のように「新卒一括採用」や「就活ルール」に縛られず、実力と経験が評価の軸になります。
高校生や保護者にとっては“将来どうなるか”が進路選びの重要な判断材料になるため、この違いを知っておくことは非常に大切です。
| 日本の大学 | アメリカの大学 | |
| 就職活動の時期 | 決まった時期に一斉 | 通年採用、柔軟に選択 |
| 採用制度 | 新卒一括採用 | 個別採用・実力重視 |
| 実務経験 | 卒業後に初めて | 在学中にインターン・CPTあり |
| 支援体制 | キャリアセンターは補助的 | キャリア支援が強力かつ個別対応 |
| 留学生支援 | 制度なし | OPT制度で最大3年の就労可能(STEM) |
日本:新卒一括採用と同時進行の「就活文化」
日本の大学生の多くは、大学3年の夏〜秋頃から「就活」を本格的に始めます。
ここでは“新卒一括採用”という制度が前提になっており、多くの企業が同時期に大学生を採用するため、就職活動も同じようなスケジュールで一斉に進みます。
- 大学3年の終わり〜4年生の夏にかけてが「就活本番」
- リクナビ・マイナビなどの就活サイトが情報源
- 内定獲得の時期が早く、卒業=就職が一般的な流れに
この仕組みによって、卒業後の「空白期間」なく安定的に職に就ける一方で、就職活動の選択肢や時期が画一的で、やりたいことの模索が難しくなるという側面もあります。
アメリカ:実践を通じてキャリアを形成
アメリカでは、新卒一括採用という考え方はほとんどありません。代わりに、インターンシップや実務経験を重ねながら「いつでも応募できる」のが基本です。
- 大学在学中のインターンシップ経験が極めて重要
- 専攻と関連する職種で実践しながら、自分の進路を固めていく
- 卒業後も空白期間を置きながら、納得いく仕事を選ぶ人も多い
特にSTEM(理工系)分野では、CPT(Curricular Practical Training)という制度で、在学中に企業で働く機会が得られます。
さらに、卒業後はOPT(Optional Practical Training)という最大1年間の就労ビザ(STEM分野は最長3年)を活用して、現地企業でフルタイムの経験を積むことも可能です。
これらの制度をうまく使えば、留学生でもアメリカでの実務経験を得てからキャリア選択ができるという大きなメリットがあります。
キャリア支援と大学ネットワークの強さ
アメリカの大学には、キャリアセンター(Career Services)と呼ばれる専門部署があり、学生の就職活動を一人ひとりサポートしています。
- 履歴書(レジュメ)の添削や模擬面接の実施
- インターンの紹介や企業説明会の開催
- 卒業生ネットワークとのマッチング支援
また、アメリカでは大学のブランド力や卒業生ネットワークが就職力に直結する傾向があり、大学ランキングが就職市場での評価にも強く影響します。
一方、日本では大学のキャリアセンターはあっても、リクナビなど外部サービスを介した就活が主流で、大学内で完結するキャリア形成の仕組みは比較的弱い傾向にあります。




【日本とアメリカの大学選び】迷ったときのヒントと考え方
「アメリカと日本、どっちの大学がいいんだろう?」
ここまで読んで、そう感じた人もいるかもしれません。
たしかに、制度や文化は大きく違うし、どちらにも魅力とハードルがあります。だからこそ大切なのは、「どちらが良いか」ではなく「どちらが自分に合っているか」を考えてみること。
完璧に決めきれなくても大丈夫。少しずつ、自分の価値観や性格、これからの生き方と照らし合わせて考えていくことが、進路選びの第一歩になります。
まずは自分の「軸」を見つけよう
大学選びをするとき、こんな視点から考えてみると、自分に合う環境が少し見えてきます。
| 比較の軸 | 日本の大学が合いそう | アメリカの大学が合いそう |
| 学び方 | 指示されたことを正確にこなすのが得意 | 自分で調べて考えることが好き |
| 授業スタイル | 黙々と聞いてメモを取るほうが落ち着く | 意見を言ったり議論するのが楽しい |
| 専攻の決め方 | 一つの専門をじっくり学びたい | いろいろ学んでから決めたい |
| 将来の見通し | 就職活動の流れに乗って早く内定が欲しい | 自分のペースで将来を探したい |
| 学びの幅 | 興味がはっきりしていて変えたくない | 興味が変わるかもしれないから幅広く学びたい |
自己診断チェックリスト
どちらが自分に合っているか、以下の7つの質問で簡単にチェックしてみましょう。
「YES」が多いほど、アメリカの大学のスタイルが向いているかもしれません。
| 質問 | YES / NO |
| 授業では、自分の意見を言ったり議論するのが苦じゃない | □ YES □ NO |
| 自分の興味が変わりやすく、将来の夢もまだ模索中だ | □ YES □ NO |
| 英語での学びに挑戦してみたいと思う | □ YES □ NO |
| 一つの専門に絞るより、幅広く学びたい | □ YES □ NO |
| 先生との距離が近くて、質問しやすい環境が理想 | □ YES □ NO |
| 周囲と同じペースより、自分のペースで進みたい | □ YES □ NO |
| 世界で活躍できる力を、大学時代に身につけたい | □ YES □ NO |
YESが4つ以上だった人は…
アメリカの大学の自由なスタイルや、多様性のある環境が、自分にフィットする可能性があります。ぜひ「進学の選択肢のひとつ」として、現実的に考えてみてください。
NOが多かった人は…
日本の大学にも、しっかりとした学びやサポートがあります。「自分の興味がはっきりしている」「安心できる環境で学びたい」なら、国内進学がぴったりかもしれません。
進路選びに悩んだら、伴走してくれる人を頼ってもいい
「日本とアメリカ、どちらが合っているのかまだよくわからない」
「専攻も将来もまだはっきりしない」
そんな迷いの中にいるのは、あなただけじゃありません。
実際、進路選びは“選ぶ”だけじゃなくて、“考えながら育てていく”プロセスでもあります。
だからこそ、自己分析や専攻選びの段階から、一緒に考えられるプロのサポートがあると安心です。
There is no Magic!! の並走型出願サポートでは、以下のようなサポートを通じて、あなたらしい進路選びを後押しします:
- 自己分析を通じて「自分の軸」を一緒に言語化する
- アメリカと日本を含めた併願戦略を一緒に設計する
- 出願に向けたエッセイ作成や推薦状、奨学金申請まで一貫してサポート
まだ「やりたいこと」が決まっていない人も、大丈夫。
むしろ、そういう人ほど、丁寧な対話やふりかえりの中で、自分らしい道が見えてくることが多いんです。
もし少しでも興味を持ったら、まずは無料相談から話してみませんか?
自分だけで抱え込まずに、一緒に考えていくことから、進路選びは始まります。

【体験談】実際にアメリカ大学へ進学した日本人の声
ここでは、実際にアメリカの大学に進学した日本人学生の声を紹介します。
どのような経緯で進学を決め、何を学び、どんな気づきがあったのか──リアルな体験は、きっと進路選びのヒントになるはずです。
探究心を貫いて世界最高峰の理系大学へ(Caltech・池田隼さん)
高校時代に見つけた自分の「知的なワクワク感」を軸に、Caltech(カリフォルニア工科大学)への進学を実現した隼さん。
日本のような「与えられた課題をこなす」学び方ではなく、アメリカでは「自分で問いを立て、深掘りしていく」探究型の学びに没頭できる環境があるといいます。
「最初から“この研究がしたい”という明確な目標があったわけではなくて。むしろ“問いを立てて掘る”という知的体験をしたくて、その土壌がある場所としてCaltechを選んだんです」
数学とコンピュータサイエンスを主専攻にしながら、課外でのAI研究にも挑戦。まさに“自由と責任”が両立するアメリカの大学の象徴のような学び方です。
学びの中で「教育学」に出会った(Denison University・あかりさん)
リベラルアーツ大学の一つ、Denison Universityに進学したあかりさんは、最初は専攻を決めずに入学。
一般教養として履修した「教育と社会正義」に関する授業がきっかけで、教育学に強い関心を持つようになりました。
「日本での進路選びは“最初に何を学ぶか”がゴール設定になりがちだけど、アメリカでは“学びながら見つけていく”ことが許されているのが大きいと思います」
授業で出会った教授とのディスカッションや、教育機関でのボランティア経験を通して、自分の価値観や将来像がクリアになっていったとのこと。リベラルアーツ教育の醍醐味を体現した事例です。
アートも音楽も本気で学べる自由な環境(North Central College・Hinataさん)
絵を描くのも、ジャズを演奏するのも好き──そんな“二足のわらじ”を履いたHinataさんが選んだのは、イリノイ州のNorth Central College。
ダブルメジャー制度を活用して、ArtとJazzを両立させています。
「日本だと“どちらかを選ばなきゃ”って感覚になりがち。でもアメリカの大学では“どちらも本気でやっていい”という空気がある。毎日が本当に楽しいです」
専攻だけでなく、寮生活や地域活動を通して多様な人々と関わることで、人間関係や価値観も広がったといいます。自由な選択肢と主体的な学びの積み重ねが、進路だけでなく人生観をも変えていくことがわかります。
▶︎体験記事を読む(North Central Hinataさん)
海外大学への進学は、一人ひとりに違うストーリーがあります。気になる体験談があれば、ぜひチェックしてみてください。
よくある質問(FAQ)
英語力が不安でも進学できる?
結論から言えば、英語力に不安があっても進学は可能です。
多くの大学には、英語力が基準に満たない学生向けに「条件付き合格」や「パスウェイプログラム」があり、進学前に語学力を補う仕組みが整っています。
また、奨学金を受けながら語学学校に通うケースもあります。
目安として、TOEFL iBTで80点以上、IELTSで6.5以上を求める大学が多いですが、出願時点で満たしていなくてもあきらめる必要はありません。
費用負担はどのくらい現実的?
アメリカの大学は、年間の学費・寮費などを合わせると500万〜800万円程度かかることもあります(州立大学や地域によって差あり)。
一方で、留学生でも応募できる奨学金や減免制度が豊富にあります。実際に、学費全額免除や生活費支援を受けながら通っている日本人学生も少なくありません。
奨学金の審査では、学業成績や課外活動、エッセイが重視されます。進学先の選定と同時に、財政支援のリサーチも重要です。
高校何年生から準備すればいい?
理想的には、高校1〜2年生から準備を始めるのがベストです。理由は以下の通りです。
- 高校の成績(GPA)が出願に必要
- 語学試験(TOEFL・IELTS)の対策に時間がかかる
- エッセイ・課外活動など「総合的な評価」に備える必要がある
特にアメリカの大学は「高校時代に何をしてきたか」を重視するため、早くから「自分らしい経験」を積むことが合格への近道になります。
とはいえ、3年生から準備して合格を勝ち取った事例もあるので、今からでも遅くありません。
終わりに|自分に合った進路を見つけるために
日本の大学とアメリカの大学、どちらが良い・悪いというわけではありません。大切なのは、「自分の興味や学び方、将来像にどちらの環境が合っているか」をじっくり見極めることです。
アメリカの大学進学というと、「英語ができないと無理そう」「学費が高そう」「情報が少なくて不安」など、ハードルの高さを感じるかもしれません。
でも実際には、英語力が発展途上でも受け入れてくれる大学はありますし、奨学金制度や支援団体を活用して費用負担を軽くすることも可能です。
なにより、正しい情報を早めに知っておくことで、十分に準備できる進路でもあります。
だからこそ、最初の一歩を一人で悩みすぎず、海外進学に詳しいプロと一緒に考えてみるのも一つの手。
自分の可能性を狭めず、自分らしい進学を見つけるために、頼れる伴走者と一緒に、進路という大きな選択に向き合ってみてください。